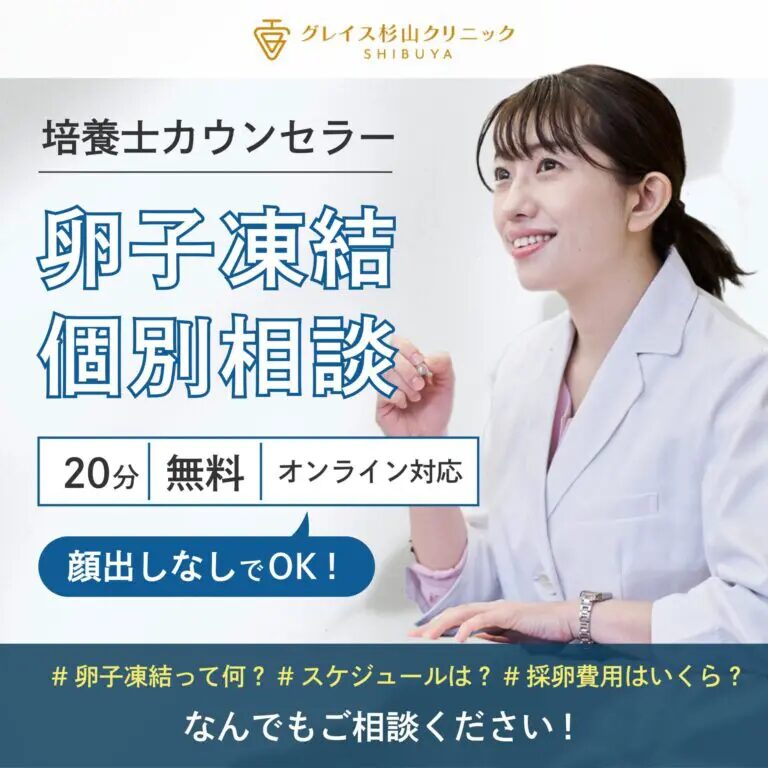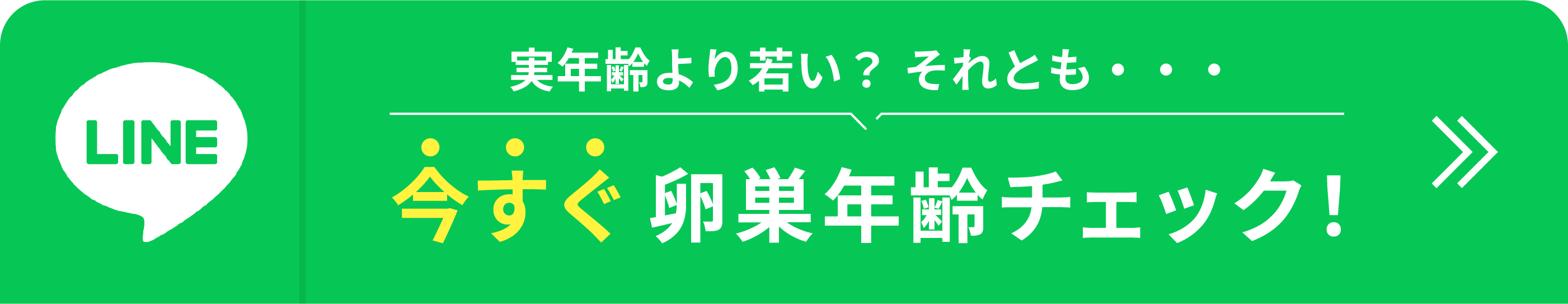「婦人科検診って実際必要なの?」「どんな病気を見つけられるの?」と疑問に思っていませんか? 婦人科系の病気は自覚症状が出にくいものが多く、早期発見が非常に重要です。 この記事では、婦人科検診の必要性を分かりやすく解説し、早期発見できる病気や婦人科健診を受けるメリットをご紹介します。さらに、20代、30代、40代以降の年代別で受けるべき婦人科検診の種類や、検診を受ける頻度、費用、注意点についても詳しく説明します。また、将来の妊娠に備える選択肢として注目されている卵子凍結についても解説します。この記事を読めば、婦人科検診の重要性や自分に合った検診内容が理解でき、安心して健診を受けるための準備ができるでしょう。
目次
婦人科検診の必要性
婦人科検診は、女性にとって非常に重要な健康管理の一つです。自覚症状がない段階で病気を早期発見し、早期治療につなげることで、健康寿命の延伸に大きく貢献します。また、将来の妊娠・出産に備え、自身の体の状態を把握するためにも不可欠です。婦人科系疾患の中には、進行すると妊娠に影響を及ぼすものもあります。定期的な検診で早期発見・早期治療を行うことで、将来の妊娠の可能性を高めることに繋がります。さらに、婦人科検診は、自分自身の体と向き合い、健康意識を高める良い機会となります。自身の体について理解を深めることで、より積極的に健康管理に取り組むことができるでしょう。
婦人科検診を受ける頻度は?
婦人科検診を受ける頻度は、年齢、既往歴、症状の有無などによって異なります。一般的には、症状がない場合、1年に1回受診することが推奨されています。ただし、これはあくまで目安であり、ご自身の年齢、既往歴、家族歴、症状の有無などを考慮し、医師と相談しながら適切な頻度を決めるようにしましょう。例えば、子宮頸がんや子宮体がん、卵巣がん、乳がんの家族歴がある場合は、より頻回に検診を受けることが推奨される場合があります。また、ピルを服用している場合も、定期的な検診が必要です。
検診を受けることで、病気を早期に発見し、適切な治療を受けることができます。また、健康状態を把握し、健康管理に役立てることもできます。 婦人科検診は、女性の健康を守る上で非常に重要です。ためらわずに、積極的に受診しましょう。
婦人科検診で早期発見できる病気
婦人科検診では、様々な病気を早期発見することができます。代表的なものとしては、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん、性感染症などがあります。これらの病気は、早期発見・早期治療によって治癒率が向上したり、進行を抑えたりすることが可能です。
子宮頸がん
子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が主な原因で発症します。初期段階では自覚症状がほとんどないため、定期的な子宮頸がん検診が重要です。細胞診やHPV検査で早期発見やリスク評価が可能です。
子宮体がん
子宮体がんは、子宮内膜に発生するがんです。子宮頸がんに比べ不正出血やおりものの異常などの症状が初期から出ることが多いです。症状がある際に、速やかに子宮内膜細胞診や超音波検査などを行うことで早期発見が可能です。
卵巣がん
卵巣がんは、初期段階では自覚症状がほとんどありません。進行すると腹痛や腹部膨満感などの症状が現れることがあります。超音波検査や腫瘍マーカー検査などで早期発見を目指します。
性感染症(STD)
性感染症(STD)は、性行為によって感染する病気の総称です。クラミジア、淋病、梅毒、HIVなど様々な種類があります。症状が現れない場合も多く、新しいパートナーと性行為をする場合は定期的な検査を受けることが大切です。おりもの検査や血液検査などで診断できます。
婦人科検診を受けるメリット
婦人科検診を受けるメリットは、早期発見・早期治療だけではありません。自身の体の状態を把握し、健康管理に役立てることができることも大きなメリットです。また、婦人科の医師に相談することで、生理に関する悩みや更年期障害、避妊など、女性特有の健康問題について適切なアドバイスを受けることができます。更年期障害の症状やPMS(月経前症候群)の症状についても相談可能です。検診結果を基に、生活習慣の改善や適切な治療を受けることで、QOL(生活の質)の向上に繋がるでしょう。

年代別おすすめ婦人科検診
年代によって婦人科検診で推奨される検査項目は異なります。ご自身の年齢に合った検診を受けることで、効果的に病気の予防や早期発見につなげることができます。
20代で受けるべき婦人科検診
20代では、性活動の開始に伴い、性感染症のリスクが高まります。また、子宮頸がんは若い世代にも発症する可能性があるため、定期的な検診が重要です。
| 子宮頸がん検診 | 子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が主な原因です。子宮頸がん検診では、子宮頸部の細胞を採取し、顕微鏡で観察することで、がん細胞や前がん病変の有無を調べます。細胞診とHPV検査を組み合わせることで、より精度の高い検査が可能です。20歳になったら、2年に1度の受診が推奨されています。 |
| 性感染症検査 | 性感染症(STD)には、クラミジア、淋病、梅毒、トリコモナス症、HIVなど様々な種類があります。多くの性感染症は自覚症状がないまま進行することが多いため、早期発見のためには検査が重要です。特に、将来の妊娠を希望する場合は、不妊症の原因となる可能性もあるため、積極的に検査を受けることをおすすめします。検査方法は、問診、内診、おりもの検査、血液検査などがあります。 |
30代で受けるべき婦人科検診
30代は、妊娠・出産を経験する方も多く、それに伴い婦人科系のトラブルも増加する年代です。子宮頸がんに加え、子宮体がんや乳がんのリスクも高まり始めるため、より包括的な検診が求められます。
| 子宮頸がん検診 | 20代と同様に、2年に1度の受診を継続しましょう。 |
| 子宮体がん検診 | 子宮体がんは、子宮内膜に発生するがんです。子宮体がん検診では、子宮内膜を採取し、顕微鏡で観察することでがん細胞の有無を調べます。 不正出血などの症状がある場合は、すぐに婦人科を受診しましょう。 |
| 乳がん検診 | 乳がんは、30代後半から増加し始めるがんです。乳がん検診には、視触診、マンモグラフィ、超音波検査などがあります。自己触診を習慣化し、定期的に乳がん検診を受けることで、早期発見・早期治療につなげましょう。乳腺症などの良性疾患の発見にも繋がります。 |
40代以降で受けるべき婦人科検診
40代以降は、女性ホルモンのバランスが変化し、更年期障害などの症状が現れ始める年代です。また、子宮体がん、卵巣がん、乳がんのリスクも高まるため、より綿密な検診が必要です。
| 子宮頸がん検診 | 引き続き、2年に1度の受診を継続しましょう。 |
| 子宮体がん検診 | 子宮体がんのリスクは40代以降さらに高まるため、不正出血が出現した際には放っておかずに婦人科を受診しましょう。 |
| 卵巣がん検診 | 卵巣がんは、初期症状がほとんどないため、早期発見が難しいがんです。卵巣がん検診では、経腟超音波検査や腫瘍マーカー検査などを用いて診断します。 定期的な検診に加え、腹部の張りや膨満感、不正出血などの症状に注意しましょう。 |
| 乳がん検診 | 乳がんのリスクは40代以降も高く、マンモグラフィと超音波検査を組み合わせた検診が推奨されます。 2年に1度の受診を心掛けましょう。 |
| 骨密度検査 | 閉経後、女性ホルモンの分泌が減少することで骨密度が低下し、骨粗鬆症のリスクが高まります。骨密度検査では、骨の強度を測定し、骨粗鬆症の診断や骨折リスクの評価を行います。 40代以降は定期的な骨密度検査を受けることで、骨粗鬆症の予防や早期治療に繋げることが重要です。 |
婦人科検診を受ける頻度は?
婦人科検診を受ける頻度は、年齢や病歴、家族歴などによって異なります。基本的には、すべての検査は1年に1度受けることが最も望ましいです。 ただし、医師の指示がある場合は、それに従いましょう。
婦人科検診の費用はどれくらい?
婦人科検診の費用は、受ける検査項目や医療機関によって異なります。自治体によっては、公費負担で受診できる場合もありますので、お住まいの自治体に確認してみましょう。 また、健康保険組合によっては補助金制度がある場合もあります。婦人科検診の費用は、医療機関によって大きく異なります。自由診療となる場合が多く、検査項目や医療機関の規模、地域などによって価格設定が異なるため、事前に複数の医療機関で見積もりを比較検討することが大切です。費用だけで判断するのではなく、医療機関の設備や医師の専門性、口コミなども考慮して選びましょう。
主な婦人科検診の費用相場
以下は、主な婦人科検診の費用相場です。あくまで目安であり、医療機関によって異なる場合があるので注意してください。
| 子宮頸がん検診 | 子宮頸がん検診は、細胞診検査が3,000円~5,000円程度、HPV検査が5,000円~10,000円程度です。全国の自治体で2年に1度、無料または低額で受診できる補助があります。 |
| 子宮体がん検診 | 子宮体がん検診は、細胞診検査が3,000円~5,000円程度です。子宮頸がん検診と同時に受診することで、費用が割引になる場合もあります。 |
| 卵巣がん検診 | 卵巣がん検診は、腫瘍マーカー検査と超音波検査を組み合わせて行うことが多く、5,000円~10,000円程度です。 |
| 性感染症(STD)検査 | 性感染症(STD)検査は、検査項目によって費用が異なります。クラミジアや淋病などの検査は、それぞれ3,000円~5,000円程度です。複数の性感染症を同時に検査できるセット検査も用意されている場合があります。 |
| 乳がん検診 | 乳がん検診は、視触診とマンモグラフィを組み合わせて行うことが多く、5,000円~10,000円程度です。全国の自治体で2年に1度、無料または低額で受診できる補助があります。 |
婦人科検診は、早期発見・早期治療のために非常に重要です。費用面も含めて、ご自身に合った検診プランを検討し、定期的に受診しましょう。費用の負担が心配な方は、自治体や健康保険組合の助成制度の利用を検討してみてください。
婦人科検診を受ける際の注意点
婦人科検診を受ける際には、いくつか注意点があります。生理中は検査ができない場合があるため、生理が終わってから1週間以内の受診がおすすめです。また、検査前には、性行為やおりもの対策の薬剤の使用を控えるようにしましょう。 リラックスして検査を受けるために、事前に気になることや不安なことを医師に相談しておくことも大切です。
症状の放置は不妊につながる?将来の妊娠に備える卵子凍結とは
婦人科系の症状を放置していると子宮や卵巣にダメージが蓄積し、将来の不妊リスクが高まる可能性があります。将来の妊娠に備えて、卵子を採取し凍結保存しておく「卵子凍結」という方法があります。卵子は加齢ととも質や数が低下していくため、若い頃の卵子を保存しておくことで、将来妊娠の可能性を高めることができます。
卵子凍結のメリット・デメリット
卵子凍結のメリットは、将来の妊娠の可能性を高めることができる点です。一方で、デメリットとしては、費用が高額であること、妊娠が100%保証されるわけではないこと、卵子採取時の合併症のリスクなどが挙げられます。
卵子凍結の費用
卵子凍結にかかる費用は、医療機関によって異なりますが、一般的には採卵費用、凍結費用、保管費用の3つに分けられます。採卵費用には、ホルモン剤の費用や超音波検査、採卵手術の費用などが含まれ、約30万円~50万円が相場です。凍結費用は約5万円~10万円、保管費用は年間約5万円~10万円程度かかります。これらの費用に加え、融解・体外受精・胚移植などの費用は別途必要となります。
卵子凍結の流れ
| 1. カウンセリング・検査 | まずは医療機関でカウンセリングを受け、卵子凍結に関する説明や、自身の状況に合わせた治療方針について相談します。その後、血液検査や超音波検査など、必要な検査を行います。 |
| 2. ホルモン剤の投与 | 排卵を促し、複数の卵胞を成熟させるために、ホルモン剤を注射します。注射は自己注射で行う場合と、通院して行う場合があります。 |
| 3. 採卵 | 成熟した卵胞から卵子を採取します。経腟超音波下に針を刺し、卵胞液を吸引する方法が一般的です。局所麻酔や静脈麻酔を用いると痛みはほとんどありません。 |
| 4. 凍結保存 | 採取した卵子は、液体窒素内で急速凍結され、長期間保存されます。 |
| 5. 将来の妊娠を希望する際 | 凍結保存された卵子を融解し、体外受精を行います。その後、受精卵を子宮内に戻す胚移植を行います。 |
まとめ
この記事では、婦人科検診の必要性について解説しました。婦人科検診は、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん、性感染症など、様々な病気を早期発見するのに役立ちます。早期発見することで、治療の負担を軽減し、より良い予後が期待できるケースも多いです。婦人科検診を受けることで、将来の妊娠に関する不安を解消することにも繋がります。
また、将来の妊娠に備える方法として、卵子凍結についても解説しました。卵子凍結は、加齢による妊娠率の低下を心配する女性にとって、将来の妊娠の可能性を残す一つの選択肢となります。費用や流れを理解した上で、検討してみましょう。婦人科健診は、自身の健康管理のために非常に重要です。この記事を参考に、ご自身の年齢や状況に合った健診を受けてみてください。
卵子凍結保管サービスはGrace Bank(グレイスバンク)がおすすめ
グレイス杉山クリニックSHIBUYAをはじめ、生殖補助医療の実績ある提携クリニックで採卵した卵子を、安心して保管できるのが卵子凍結保管サービスGrace Bank(グレイスバンク)です。クリニックの保管とは異なり、もし将来転勤などで居住地が変わっても、凍結した卵子を使える安心感があります。
【Grace Bank(グレイスバンク)の特徴】
- 確かな実績を持った経験豊富な生殖補助医療クリニックと提携。将来の体外受精時には、凍結卵子をどの提携クリニックでも利用可能
- クリニック内の小型タンクによる保管とは異なり、さい帯血バンクのステムセル研究所と提携し、25年以上無事故を誇る専用大型タンクで一括管理
- 保管施設は地震や津波に強いエリアに設置され、停電対策も万全、安心のシステムで大切な卵子を保管
保管費用は初期費用として55,000円(税込)、保管費用として年払い38,500円(税込)または月払い3,850円(税込)の2つのプランからお選びいただけます。
卵子凍結について興味がある方・実際に検討されている方は、ぜひGrace Bankの無料セミナー等もご活用ください。より詳しく卵子凍結の相談・検討をしたい場合は無料の個別相談がおすすめです。
- Grace Bank所属スタッフが、グレイスバンクのサービス内容・ご利用の流れ・お手続き・クリニック選び等のご不明な点について個別にお応えします。
- グレイス杉山クリニックSHIBUYAで実際に卵子凍結業務にあたる培養士カウンセラーが、卵子凍結自体のご質問や、医学的なご相談に個別でお受けします。

名倉 優子 なぐら ゆうこ
日本産科婦人科学会専門医
グレイス杉山クリニックSHIBUYA (東京都渋谷区)
杉山産婦人科の医師・培養士による技術を用いた質の高い診療を提供。
将来の妊娠に備えたプレコンセプションケアと卵子凍結にフォーカスした診療。
スタッフは全員女性。明瞭な料金設定も人気!