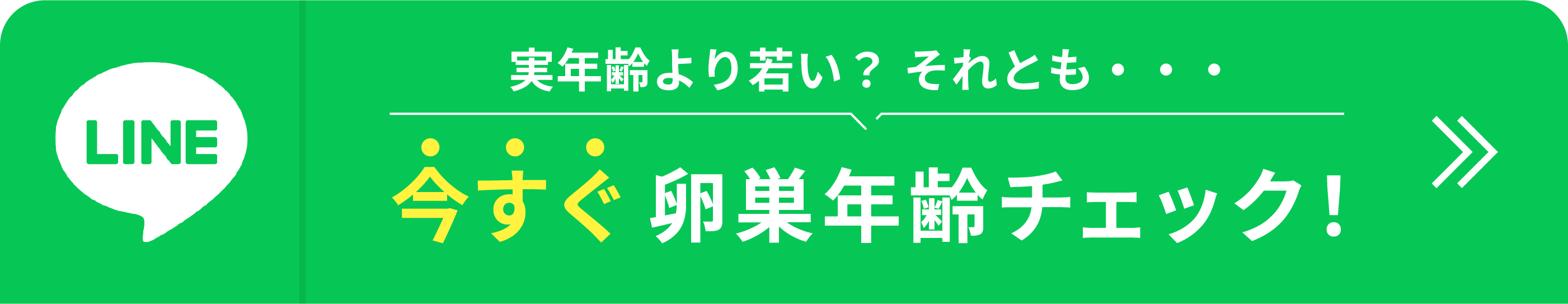「卵子凍結の費用がわかりにくい…」と感じていませんか?本記事では、その疑問を解消するために、卵子凍結の料金体系を解説します。費用が不透明に感じるのは、クリニックごとの表示方法の違いや、初期費用と保管費用(維持費用)の混同が主な原因です。この記事を読めば、卵子凍結にかかる総額費用、検査から採卵、保管、将来的な融解・移植までの内訳を明確に理解できます。さらに、助成金制度や費用を抑えるポイントもご紹介。安心して卵子凍結を検討できるよう、必要な情報を解説していきます。
目次
卵子凍結の費用がなぜわかりにくいと感じるのか
「卵子凍結を検討しているけれど、費用がいくらになるのか、なぜこんなにわかりにくいのだろう?」そう感じている方は少なくありません。実際、卵子凍結にかかる費用は、その性質上、一概に「いくら」と明言しにくい側面があります。しかし、その「わかりにくさ」には明確な理由が存在します。ここでは、多くの人が卵子凍結の費用に対して不安や疑問を抱く具体的な原因を深掘りし、その背景にある構造を解説します。
不透明な料金体系が不安を生む理由
卵子凍結の費用がわかりにくいと感じる最大の理由の一つは、その料金体系が必ずしも透明ではないことにあります。多くの医療行為と同様に、卵子凍結も複数のステップと、それに伴う様々な費用で構成されています。しかし、それらの費用がクリニックによって細かく分類されていたり、あるいは逆に大まかに「セット料金」として提示されていたりするため、具体的に何にいくらかかっているのかが把握しにくいのが現状です。
例えば、初診時の検査費用、排卵誘発剤の薬剤費用、採卵手技費用、麻酔費用、凍結処理費用、そして凍結した卵子の保管料など、多くの項目があります。これらの項目が個別に表示されている場合でも、それぞれの単価が明確でなかったり、総額がいくらになるのかがすぐに計算できなかったりすることがあります。また、特定のオプション検査や追加処置が必要になった場合に、後から追加費用が発生する可能性があることも、ユーザーにとっての不安要素となります。
このような不透明さは、「結局、総額でいくら必要なのだろう?」「提示された費用以外に、隠れた費用があるのではないか?」といった疑問や不安を生み、卵子凍結への一歩を踏み出すことを躊躇させてしまう原因となっているのです。
クリニックごとの表示方法の違い
卵子凍結を提供するクリニックは増えていますが、それぞれのクリニックが独自の料金表示方法を採用していることも、費用をわかりにくくしている大きな要因です。あるクリニックでは「基本パッケージ」として採卵から初期凍結までをまとめた料金を提示する一方で、別のクリニックでは検査費用、薬剤費用、採卵費用などを細かく分けて表示するといった違いが見られます。また、採卵できた卵子の個数によって初期費用や保管費用が異なってくるケースもあります。
さらに、年間保管料が月額表示なのか年額表示なのか、何年分の保管料が初期費用に含まれているのか、といった細かな点もクリニックによって異なります。これらの表示方法の違いは、複数のクリニックを比較検討する際に、単純な横並び比較を非常に困難にします。ユーザーは、それぞれのクリニックの料金表を詳細に読み込み、項目を照らし合わせながら、比較・計算する必要があるため、多大な時間と労力を要することになります。
この比較の難しさが、結果として「結局どのクリニックが良いのか、費用面でどこが適正なのかが判断できない」という混乱を招き、卵子凍結への決断を遅らせる原因にもなりかねません。
初期費用と保管費用(維持費用)の混同
卵子凍結の費用を考える上で、特に注意が必要なのが「初期費用」と「保管費用(維持費用)」の混同です。多くのユーザーは、まず採卵や凍結処理にかかる「初期費用」に注目しがちですが、卵子凍結は凍結した卵子を将来使用するまで保管し続ける必要があるため、毎年発生する「保管費用(維持費用)」も重要な要素となります。
しかし、クリニックによっては初期費用の中に数年分の保管料が含まれているケースもあれば、初期費用とは別に初年度から年間保管料が発生するケースもあります。また、保管期間が長くなればなるほど、維持費用が総額に占める割合は大きくなります。この初期費用と維持費用の区別が曖昧であったり、維持費用の説明が不十分であったりすると、ユーザーは「初期費用だけ見て決めたら、後から年間保管料の高さに驚いた」といった事態に陥りかねません。
卵子凍結は、一度行えば終わりではなく、将来の融解・移植までを見据えた長期的な計画が必要です。そのため、初期費用だけでなく、将来にわたって発生する維持費用まで含めた総額を正確に把握することが、費用に関する不安を解消し、納得のいく決断をする上で不可欠となります。
卵子凍結の総額費用を明瞭に理解する
卵子凍結にかかる費用は、一見すると複雑で理解しにくいと感じるかもしれません。しかし、その全体像を把握し、構成要素を一つずつ見ていくことで、不安は解消されます。この章では、卵子凍結にかかる総額費用の目安と、その内訳を明確に解説します。
卵子凍結の費用相場と全体像
卵子凍結にかかる総額費用は、クリニックや個人の状況によって大きく異なりますが、一般的には初期費用として30万円から50万円程度が目安とされています。これには、事前の各種検査、排卵誘発、採卵、そして卵子の凍結保存費用が含まれます。
しかし、費用はこれで終わりではありません。凍結した卵子を将来使用するまで保管し続けるための「保管費用(維持費用)」が毎年発生します。さらに、実際に卵子を使用する際には、融解費用や体外受精、胚移植、妊娠判定といった費用が別途必要になります。
つまり、卵子凍結の費用は、「初期費用」「保管費用(維持費用)」「将来的な融解・移植費用」の3つの段階に分けて考えることで、より明確に全体像を把握できます。この全体像を理解することが、費用に対する不安を軽減する第一歩となるでしょう。
初期費用と保管費用(維持費用)の内訳
卵子凍結の費用を理解する上で最も重要なのが、「初期費用」と「保管費用(維持費用)」の明確な区別です。この二つを混同してしまうと、費用がわかりにくいと感じる大きな原因となります。
初期費用とは、主に卵子を採卵し、凍結保存するまでにかかる一連の費用を指します。具体的には、事前の検査費用、排卵誘発剤などの薬剤費用、採卵手術費用、そして凍結処理費用や初期の保管費用が含まれます。これは基本的に一度だけ発生する費用です。
一方、保管費用(維持費用)は、凍結された卵子を専門の施設で安全に保管し続けるために、毎年継続的に発生する費用です。この費用は、保管期間が長くなるほど総額が増加するため、長期的な視点での計画が重要になります。
次の章以降では、これらの初期費用と維持費用について、さらに詳細な内訳を解説していきます。
卵子凍結の初期費用を詳しく解説
卵子凍結を検討する際に、まず気になるのが初期費用です。この初期費用には、採卵を行う前段階の検査から、実際に卵子を採取し凍結するまでの費用が含まれます。クリニックによって料金体系が異なるため「わかりにくい」と感じる方も少なくありませんが、ここではその内訳を詳しく解説し、全体像を把握できるようにします。
検査費用
卵子凍結を安全かつ効果的に進めるためには、事前の詳細な検査が不可欠です。これらの検査は、現在の身体の状態や卵巣機能、感染症の有無などを確認するために行われます。
初診時の検査内容と費用
初診時には、問診や診察の他に、いくつかの基本的な検査が行われます。これには、超音波(エコー)検査による子宮や卵巣の状態確認、卵胞の数の把握が含まれます。また、採血によるホルモン値の測定も同時に行われることが一般的です。これらの検査によって、卵子凍結が可能かどうか、またどのような排卵誘発方法が適しているかなどの判断材料が得られます。初診時の検査費用は、クリニックや検査項目によって異なりますが、数千円から数万円程度が目安となります。
ホルモン検査や感染症検査の費用
より詳細なホルモン検査では、卵巣の予備能を示すAMH(抗ミュラー管ホルモン)や、卵胞の発育に関わるFSH(卵胞刺激ホルモン)、LH(黄体形成ホルモン)、エストラジオール(E2)などの測定が行われます。これらの数値は、排卵誘発剤の量や方法を決定する上で非常に重要です。
また、感染症検査は、採卵時の安全確保や凍結卵子の保管、将来的な妊娠の安全のために必須とされています。B型肝炎、C型肝炎、梅毒、HIVなどのウイルス検査が含まれ、これらの検査結果によっては、採卵の実施時期や方法が調整されることがあります。ホルモン検査や感染症検査は、それぞれ数千円から1万円程度の費用がかかることが多く、複数の項目をまとめて行う場合は数万円になることもあります。
採卵費用
採卵は、卵子凍結における最も重要なステップの一つです。このプロセスには、卵子を育てるための排卵誘発から、実際に卵子を採取する手技、そして麻酔の費用が含まれます。
採卵手術にかかる費用
採卵手術とは、成熟した卵子を卵巣から採取する医療行為そのものを指します。これは、超音波で卵巣の状態を確認しながら、細い針を使って卵胞内の卵子を吸引する処置です。採卵の難易度や採取する卵子の数によって費用が変動するクリニックもありますが、多くの場合、一回の採卵処置として一定の費用が設定されています。
麻酔費用とその種類
採卵処置は痛みを伴う可能性があるため、麻酔が用いられます。麻酔の種類には、局所麻酔、静脈麻酔(全身麻酔に近い状態)などがあり、クリニックの方針や患者さんの希望、卵胞の数などによって選択されます。局所麻酔は費用が比較的安価ですが、静脈麻酔は専門の麻酔科医が担当する場合などもあり、その分費用も高くなる傾向にあります。麻酔費用は、数万円から10万円以上かかることもあります。
排卵誘発剤の薬剤費用
採卵に先立ち、卵子を複数個育てるために排卵誘発剤が使用されます。これは、自然周期では通常1個しか排卵しない卵子を、複数個成熟させることを目的としています。排卵誘発剤には注射薬が主流で、薬剤の種類(ゴナドトロピン製剤など)、使用量、投与期間によって費用が大きく変動します。個人差が大きく、十数万円かかることも珍しくありません。薬剤費用は、卵子凍結の初期費用の中でも特に高額になりやすい項目の一つです。
凍結保存費用
採卵によって得られた卵子は、将来の使用に備えて凍結保存されます。この段階にも、初期費用として特定の費用が発生します。
初期の凍結処理にかかる費用
採卵された卵子は、特殊な方法で凍結処理されます。現在、卵子の凍結には「ガラス化法」と呼ばれる急速凍結法が主流であり、これにより卵子の生存率が高く保たれます。この凍結処理には、専門的な技術と設備が必要となるため、その費用が発生します。凍結する卵子の数によって費用が変わるクリニックもあれば、一律の費用を設定しているクリニックもあります。
初期保存期間の費用
凍結処理された卵子は、専用のタンクで液体窒素を用いて保管されます。多くのクリニックでは、凍結処理費用に加えて、最初の一定期間(例えば1年間)の保管費用が初期費用に含まれているか、別途初期費用として請求されます。この初期保存期間が終了した後は、年間維持費用として別途費用が発生することになります。初期保存期間の費用は、数万円程度が一般的です。
卵子凍結の維持費用と将来的な費用
卵子凍結は、採卵・凍結といった初期費用だけでなく、凍結した卵子を保管し続けるための維持費用、そして将来的にその卵子を使って妊娠を目指す際に必要となる融解・移植費用が発生します。これらの費用を明確に理解することで、卵子凍結の総額をより正確に把握できるようになります。
卵子保管の年間維持費用
卵子凍結の初期費用を支払った後も、凍結卵子を安全に保管し続けるためには年間で維持費用が発生します。これは、液体窒素タンクの維持管理費、設備費、人件費などが含まれる費用です。多くのクリニックでは、契約時に最初の一定期間(例えば1年間)の保管料が含まれていることがありますが、それ以降は毎年更新料として支払いが発生するのが一般的です。
保管期間による費用の変動
卵子保管の年間維持費用は、クリニックによって異なりますが、年間数万円から10数万円が相場です。長期にわたって保管するほど、総額としての維持費用は高くなります。例えば、年間5万円の保管料であれば、5年間保管すると25万円、10年間保管すると50万円が必要になる計算です。多くのクリニックでは、保管期間を1年、3年、5年、10年といった単位で選択できる場合がありますが、長期契約による割引は稀で、基本的には年間単価は変わりません。保管契約は通常自動更新ではなく、毎年、または設定された期間が終了する前に更新の意思確認が行われます。更新しない場合は、凍結卵子の破棄となることがほとんどです。
保管方法と費用の関係
費用差は主にクリニックの料金設定や提供されるサービス内容に起因します。一部のクリニックでは、自院で保管せず、専門の外部施設に保管を委託しているケースもあります。重要なのは、凍結卵子が適切に管理・保管されているかという点であり、費用だけでなく施設の信頼性も考慮に入れるべきです。
将来的な融解と移植にかかる費用
卵子凍結は、あくまで将来の妊娠に備えるための準備段階です。実際にその卵子を使って妊娠を目指す際には、別途「融解・移植」にかかる費用が発生します。これは、凍結卵子を融解し、体外受精を経て胚を培養し、子宮に戻すまでの一連の治療にかかる費用であり、一般的な体外受精治療の費用に準じます。
融解費用と培養費用
凍結卵子を使用する際、まず必要となるのが「融解費用」です。これは、凍結保存されていた卵子を体温に近い温度に戻し、次のステップに進めるための費用です。融解された卵子は、精子と受精させるための準備に入ります。凍結卵子の場合は、ほとんどのケースで「顕微授精(ICSI)」が必要となります。顕微授精とは、細い針を使って卵子に直接精子を注入する方法で、この手技にも費用が発生します。受精が確認された後は、培養液の中で胚を育てる「培養費用」がかかります。培養期間は数日間で、初期胚(受精後2~3日目)で移植するか、より成長させた胚盤胞(受精後5~6日目)で移植するかによって、培養費用や成功率が変動することがあります。
胚移植費用と妊娠判定費用
培養された胚を女性の子宮に戻すのが「胚移植費用」です。この手技は、超音波ガイド下で細いカテーテルを使って行われます。移植後、約10日から2週間後に妊娠しているかどうかを確認するための「妊娠判定費用」が発生します。これは血液検査や尿検査などで行われ、妊娠ホルモンの値を確認します。これらの融解・培養・胚移植・妊娠判定までの一連の費用は、クリニックや治療内容によって大きく異なりますが、合計で50万円から100万円以上かかることも珍しくありません。また、一度の移植で妊娠に至らない場合は、再度融解・培養・移植を行う必要があり、その都度費用が発生することを理解しておく必要があります。
卵子凍結の費用を抑える方法と助成金

国や地方自治体の助成金制度
卵子凍結に関する国の支援
卵子凍結の費用負担を軽減するためには、国や地方自治体の助成金制度を積極的に活用することが重要です。特定の疾患を持つ方(例えば、がん治療前の生殖機能温存を目的とした卵子凍結など)に対しては、一部の公的医療機関や自治体が助成を行っている場合があります。これは、将来の妊娠の可能性を残すための医療行為として位置づけられています。一般的な「社会的卵子凍結」については、東京都をはじめとする自治体で助成金制度が開始されており、今後の動向に注目が集まっています。
お住まいの地域の助成金を確認する方法
お住まいの市区町村が独自に卵子凍結の助成制度を設けている場合があります。これは、少子化対策や女性のライフプラン支援の一環として、近年増加傾向にあります。助成金の有無や内容は自治体によって大きく異なるため、自治体のウェブサイトや、担当部署への問い合わせを通じて、最新の情報を確認しましょう。また、卵子凍結を行うクリニックが、地域の助成金制度に関する情報提供や申請サポートを行っている場合もあるため、カウンセリング時に相談してみるのも良い方法です。申請には条件や期間が定められていることが多いため、早めの情報収集と準備が肝心です。
費用を比較検討するポイント
複数のクリニックから見積もりを取る
卵子凍結の費用はクリニックによって大きく異なります。そのため、複数のクリニックから詳細な見積もりを取得し、比較検討することが、費用を抑える上で非常に有効です。見積もりを取る際は、単に総額だけでなく、初期費用、維持費用、そして将来的な融解・移植費用まで含んだ内訳が明記されているかを確認しましょう。また、提示された費用以外に、追加で発生する可能性のある費用(麻酔の種類、薬剤の量、オプション検査など)についても事前に確認しておくことが大切です。
パッケージプランと個別料金の比較
クリニックによっては、採卵から一定期間の凍結保存までをまとめたパッケージプランを提供している場合があります。パッケージプランは、総額が明確で安心感がある一方で、途中で治療を中断した場合でも費用が返還されないケースがあるため注意が必要です。一方、必要な処置ごとに費用が発生する個別料金は、無駄な費用を抑えられる可能性がありますが、総額が見えにくいという側面もあります。ご自身のライフプランや経済状況に合わせて、どちらの料金体系がよりメリットが大きいかを慎重に比較検討しましょう。
追加費用が発生するケースと注意点
オプション検査や追加処置の費用
卵子凍結の基本費用以外に、オプション検査や追加処置の費用が発生するケースがあります。例えば、より詳細なホルモン検査、遺伝子検査、または採卵時の麻酔の種類変更(静脈麻酔から全身麻酔へなど)によって追加費用が生じることがあります。また、排卵誘発剤の反応が悪く、薬剤の追加投与が必要になった場合や、採卵回数を増やす場合にも費用が加算されます。これらの追加費用については、契約前にクリニックから詳細な説明を受け、納得した上で進めることが重要です。
キャンセル料や再診料
予期せぬ体調の変化やスケジュールの都合で、予約を変更・キャンセルする場合、キャンセル料や再診料が発生することがあります。特に採卵周期に入ってからのキャンセルは、準備にかかった費用(薬剤費など)が請求される可能性が高いため注意が必要です。また、定期的な診察や相談のための再診時にも、別途再診料が発生することが一般的です。クリニックのキャンセルポリシーや再診料の規定を事前に確認し、不測の出費を避けるための準備をしておきましょう。
クリニック選びと卵子凍結の費用
卵子凍結の費用がわかりにくいと感じる方にとって、費用はクリニック選びの大きな要素となるでしょう。しかし、費用だけでクリニックを選ぶことは、後悔につながる可能性もあります。ここでは、費用とサービスのバランスを考慮したクリニック選びのポイントを解説します。
費用だけでクリニックを選ばない理由
卵子凍結は、将来の妊娠に備えるための大切な医療行為です。そのため、費用が安いという理由だけでクリニックを選ぶことは避けるべきです。最も重要なのは、医療の質と安全性です。
具体的には、医師の経験や技術、胚培養士の専門性、使用される医療機器の品質、そして卵子を保管する環境などが挙げられます。質の低い医療は、採卵できる卵子の数が少なかったり、凍結後の生存率が低かったり、さらには将来の妊娠率に影響を与えたりする可能性があります。また、カウンセリング体制やアフターフォローの充実度も、長期的な安心感に繋がります。
費用だけでなく、クリニックの設備、技術力、実績、そしてスタッフの対応やサポート体制など、総合的な視点で検討することが、後悔のない卵子凍結を実現するために不可欠です。
料金体系が明瞭なクリニックの見つけ方
卵子凍結の費用がわかりにくいと感じる原因の一つに、クリニックごとの料金表示の違いがあります。料金体系が明瞭なクリニックを選ぶことは、安心して治療を進める上で非常に重要です。
料金体系が明瞭なクリニックは、一般的に以下の特徴を持っています。
- ウェブサイトに詳細な料金表が掲載されている:初期費用、保管費用(維持費用)、オプション費用などが具体的に明記されているかを確認しましょう。
- 初診時やカウンセリングで費用について丁寧に説明してくれる:不明点がないか、追加費用の可能性についても事前に教えてくれるクリニックは信頼できます。
- 見積書を具体的に提示してくれる:採卵数に応じた費用や、麻酔の種類による費用の違いなど、詳細な内訳がわかる見積書を発行してくれるか確認しましょう。
- パッケージプランと個別料金の選択肢がある:ご自身の希望や予算に合わせて柔軟に選べる体制があるかもポイントです。
複数のクリニックを比較検討する際は、提示された見積もりだけでなく、その料金に含まれるサービス内容までしっかり確認することが大切です。
卵子凍結の費用とサービスのバランス
卵子凍結の費用は決して安くありませんが、費用が高いからといって必ずしも最良のクリニックとは限りませんし、安すぎるクリニックにも注意が必要です。重要なのは、ご自身の希望するサービス内容と予算のバランスを見極めることです。
例えば、最新の設備や高度な技術を求めるのであれば、それに見合った費用がかかるのは当然です。一方で、不要なオプションや過剰な検査が含まれていないか、内容を精査することも大切です。
費用とサービス内容を比較検討する際には、以下の点を考慮しましょう。
- ご自身の健康状態や年齢:必要な検査や処置が異なる場合があります。
- 将来の計画:何個の卵子を凍結したいか、どのくらいの期間保管したいかなど。
- クリニックのサポート体制:精神的なサポートや情報提供が充実しているか。
最終的には、費用だけでなく、クリニックへの信頼感や安心感、そしてご自身が納得して治療を受けられるかが、最も重要な選択基準となるでしょう。
まとめ
卵子凍結の費用は、初期費用、保管費用(維持費用)、そして将来の融解・移植費用と多岐にわたり、一見すると複雑でわかりにくいと感じるかもしれません。しかし、その内訳やクリニックごとの料金体系、さらには国や地方自治体の助成金制度を事前に理解することで、不安は大きく軽減されます。費用だけでクリニックを選ぶのではなく、明瞭な料金提示と信頼できる医療サービスを総合的に比較検討することが、後悔のない選択に繋がります。本記事が、あなたが卵子凍結を安心して検討し、納得のいく未来への一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
卵子凍結について興味がある方・実際に検討されている方は、ぜひGrace Bank(グレイスバンク)の無料セミナー等もご活用ください。より詳しく卵子凍結の相談・検討をしたい場合は無料の個別相談がおすすめです。

卵子凍結の流れや費用はもちろん、卵子凍結でよくいただくお悩みや不安を、個別にお答えします。また、実際に卵子凍結した経験者から、体験談を踏まえたご相談も可能です。
| 担当 | グレイスバンク所属スタッフ (卵子凍結経験者を選択可) |
|---|---|
| 費用 | 無料 |
| 所要時間 | 5~30分間 |
| 実施方法 | zoom(カメラOFFでOK) |
| 対応日時 | 30分刻みで予約受付中 |

名倉 優子 なぐら ゆうこ
日本産科婦人科学会専門医
グレイス杉山クリニックSHIBUYA (東京都渋谷区)
杉山産婦人科の医師・培養士による技術を用いた質の高い診療を提供。
将来の妊娠に備えたプレコンセプションケアと卵子凍結にフォーカスした診療。
スタッフは全員女性。明瞭な料金設定も人気!