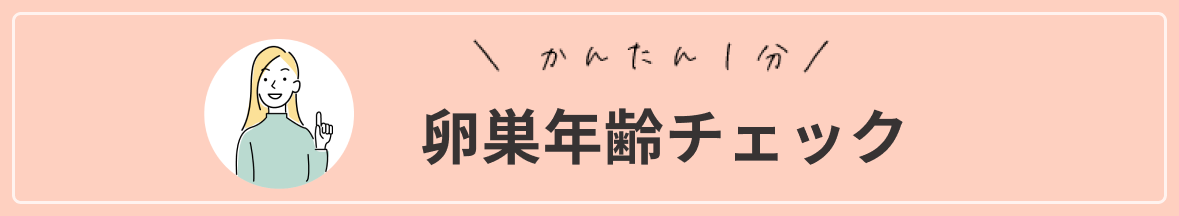東京都が健康な女性の将来の備えとしての「卵子凍結」支援を開始
東京都の小池百合子知事は、9月15日、健康な女性の卵子凍結について自治体として支援を開始すると発表しました。
これまで東京都では、がんの治療のために女性が妊娠するための力(妊孕性:にんようせい)を温存する方法として、卵子凍結への支援をしていましたが、健康な女性の将来への備えとしての卵子凍結を支援するのは初めてです。
※2021年度より、「妊孕性温存療法」に対して都道府県が助成を行うようになっています。

東京都が、女性の出産とキャリアの両立が難しい点などを考慮して、女性の選択肢を増やすために支援を開始したことは、とても画期的なことです。
自治体が卵子凍結の支援をするのは、とても珍しいことですが、実は東京都が初めてではありません。実は2015年度に千葉県の浦安市が、市内に住む20~34歳の女性を対象に7割の金額を支援する制度を導入していました。ただ、この制度は3年間だけで、2018年には終了しています。
その点からすると、今回の東京都の支援の枠組みは、規模や影響力から見ても浦安の事例を超えるものです。
また日本受精着床学会は、12月8日、将来に妊娠・出産をする可能性を考えて卵子凍結を行った女性は、2021年に都内で1135件(11施設)にのぼると発表しました。
参考)http://www.jsfi.jp/information/info_221208.html
この数値は、調査を行った日本受精着床学会の医師も驚く数値で、現在は妊娠できないけれど、将来に向けて可能性を残したいという女性たちが、とても多いことを裏付ける結果になりました。
アメリカでは「卵子凍結」を福利厚生に
卵子凍結に注目が集まるのは日本だけではありません。
アメリカでは2009年に475人の女性が卵子凍結を行いましたが、その数は10年後に1万6000人を超えています(SART調査)。
アメリカは国や自治体で、このような卵子凍結への補助はありませんが、民間の企業が福利厚生の一環として2014年頃から社員に向けて支援をするようになりました。

2万人以上の社員のいる大企業でみると、支援を行なっている企業は2020年には19%になっていて、2015年の6%から大幅に増加。珍しいものではなくなってきているのです。(Mercer調査)
日本でも始まる卵子凍結支援
日本では、2021年5月にメルカリが卵子凍結の費用を200万円を上限に負担する制度を正式にスタートしました。
またネット広告事業のサイバーエージェントや、通信販売のジャパネットホールディングスは最大40万円を補助する福利厚生を導入しており、日本でも人材の獲得という観点から、企業主導の支援がじわじわと広がっています。
グレイスグループは不妊治療の一因となっているヘルスリテラシー向上・卵子凍結の有用性の理解促進・女性活躍推進における福利厚生制度設計の支援を行っています。ここで企業様への導入事例をご紹介します。
今回東京都の卵子凍結の支援開始は。女性たちだけでなく、企業も注目する制度であることは間違いありません。
まとめ
現在は仕事を優先したいから、今のところ妊娠や出産を予定していなくても、いつかは…とお考えの皆さんにとって、ひとつの大きな選択肢となるのが卵子凍結保管です。妊娠力の高い良質な卵子を凍結保存しておくことは、将来の妊娠に備えた方法として効果的です。

Grace Bankでは、有名不妊治療クリニックとの連携、安心の保管システムを採用し、皆様の選択肢を大切にお守りいたします。ご質問、ご不明な点はGrace Bankまでお問い合わせください。