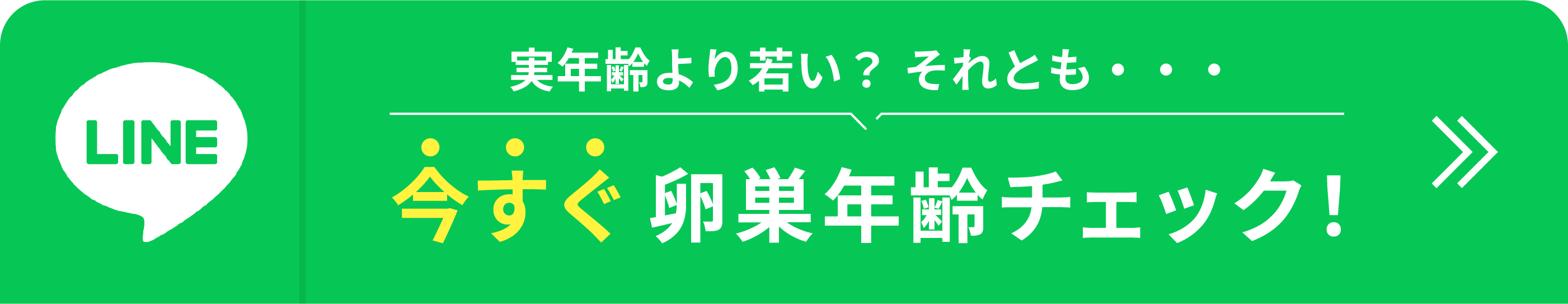昨年4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、保険適用されることとなり、大変注目が集まっている不妊治療。さまざまな企業においても、社員が不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりに取り組む動きが広がっています。厚生労働省が推奨する「不妊治療と仕事の両立支援」(※1)を実践することは、不妊治療を理由とした離職防止、社員の安心感やモチベーションの向上、新たな人材を引き付けることなどにつながり、企業にとっても大きなメリットが考えられます。
(※1)厚生労働省「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」
2023年9月15日、東京都が卵子凍結に最大30万円の助成を発表したニュースをご存じの方、耳にした方も多いのではないでしょうか?
東京都は15日、将来の妊娠を望む人への具体的な支援策を公表した。凍結した卵子を活用した生殖補助医療を利用する人に対し最大150万円を助成する。都は2022年の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産むとされる子供の数)が1.04と全国で最も低い。妊娠を希望する人への支援を広げ、将来の妊娠の可能性を残せるようにする。
対象となるのは妻の年齢が43歳未満で、凍結卵子を使った生殖補助医療を受ける夫婦。1回につき25万円を上限に最大6回まで助成する。10月16日から申請を受け付ける。
加えて18〜39歳の都内在住の女性が都の指定する医療機関で卵子の凍結保存をする場合、最大30万円を助成する。都の調査への協力や説明会への参加が必要で、凍結する年度に上限20万円、次年度以降は年に2万円を最大5年間助成する。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC1564G0V10C23A9000000/
日本経済新聞2023年9月15日より:東京都、凍結卵子の生殖補助医療に最大150万円助成
目次
約35%が離職…不妊治療と仕事の両立の難しさの実態とは?
厚生労働省発表のデータ(※2)によると、不妊治療と仕事との両立について、両立しているとした回答した方は全体の約50%ですが、約35%は仕事を離職したとのことで、多くの方が不妊治療と仕事との両立について悩んでいる実態が分かっています。
※2 厚生労働省「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」
「不妊治療に係る実態については「ほとんど知らない」「全く知らない」とする労働者が8割近くいるとともに、企業の67%は不妊治療を行っている社員を把握していないという実態があります。そうした中で、不妊治療と仕事との両立について、両立しているとする者は約5割しかおらず、約35%は仕事を辞めたり、雇用形態を変えていました。」
厚生労働省「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」P9より
このような現状や、実態を踏まえたならば、早期に不妊治療と仕事の両立支援策を、社員に提示することが急務とも言えます。
不妊治療と仕事の両立支援のための制度や取り組みにはどのようなものがある?
不妊治療は、多くの場合、治療に費やす「時間」または「お金」がかかるのが現実です。したがって、企業側は、従業員のために「時間やゆとり」を創出したり「金銭的なサポート」を行うことが、支援体制として求められることです。より具体的にみていきましょう。
不妊治療のために利用可能な休暇・休職制度
- 不妊治療に特化した休暇制度
- 不妊治療に特化しないが、不妊治療も対象となる休暇制度
- 失効年次有給休暇の積立制度
- 半日単位・時間単位の年次有給休暇の取得制度
- 不妊治療に特化した休職制度
柔軟な働き方に資する制度
- フレックスタイム制
- 時差出勤制度
- 短時間勤務制度
- テレワーク
- 再雇用制度
不妊治療に関わる費用の助成制度
- 不妊治療費に対する補助金制度
- 不妊治療費に対する貸付金制度
不妊治療を受けながら働き続けられる職場作りの第一歩とは?~セミナー開催のすすめ~
突然ですが、クイズです。

不妊の原因は、女性側の検査で特定できる…〇か×か?
不妊治療を検討したことがある方や、治療中の方ならば答えはすぐに「× 男女ともに検査が必要」とお答えになったかと思います。不妊治療は、一般的な風邪などの診療や治療と異なり、特殊な検査や進め方が存在し、しかも万人に異なるという事情があります。例えば、不妊治療が検査から始まる場合ですと、女性は問診・内診・超音波検査を行い、さらに基本検査に進みます。男性ですと、問診と精液検査のみの場合がほとんどです。検査は女性が1〜3カ月、男性は1回で済むこともあります。
このように、「えーそうなの?」「初めて知りました」という情報を、不妊治療を今まで知るきっかけのなかった方にも周知することで、相手の状況を想像することが可能になるかと思います。相手の状況を想像することができたら、もし仲間から急な予定調整などをお願いされても、「今は大変なときかもしれない、応援しよう」というあたたかい気持ちでいることができますよね。
自分は当事者でなくても、相手の立場にたって事を考えることができたら、まさに「one for all, all for one」の精神です。
相手の立場を理解するために、情報を共有することは、とても円滑な人間関係や職場の風土を生み出すきっかけになるのではと思います。そのひとつの有効的な方法として、「セミナー」を開催することが考えられます。
では、実際に企業ではどのような「セミナー」が行われているのか?
いくつかの導入事例をみていきます。
例えば、旭運輸株式会社さんでは、下記のような「女性の健康についてのセミナー」を実施しています。
「女性のライフステージごとの疾病、妊娠・出産、不妊等、健康全般について、心理カウンセラーが講師となり、管理職には女性社員への対応の留意点を認識してもらうため、また女性社員には自身の健康等について知識を深めてもらうためのセミナーをそれぞれ開催している」
厚生労働省「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」P24より
住友生命保険相互会社さんでは、下記のような「不妊治療についてのオンラインセミナー」を実施しています。
「不妊治療全般の基本的な知識から、仕事と不妊治療との両立、不妊治療に対する職場サポート・心構え、女性特有の健康課題等をテーマに、計5回実施した。特に職場のサポート・心構え は管理職にも受講を勧め、職場風土の醸成を図った」
厚生労働省「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」P33より
では、わが社の場合は…?女性活躍推進のための福利厚生はグレイスグループ
「セミナー」はどのように行えばよいのでしょうか?
実際に、どのような内容で開催すればよいのか…お悩みのご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか?そのような方に、朗報をお伝えします。
グレイスグループは不妊治療の一因となっているヘルスリテラシー向上・卵子凍結の有用性の理解促進・女性活躍推進における福利厚生制度設計の支援を行っています。
不妊のメカニズムや女性の身体について、専門医と連携してセミナーを実施し、社員様のリテラシー向上を図ります。また管理職・役員様向け研修として、不妊治療の基本や両立の課題、必要な配慮などについての研修を行います。
おかげさまで、セミナ―満足度は、★4.6を頂いております。(※セミナ―実施企業5社651件のアンケート結果より算出)
【導入事例】ジャパネットホールディングス様
冒頭にもご紹介した通りに、卵子凍結には大変注目が集まっています。福利厚生として「卵子凍結」を導入する法人様も増えております。実際「卵子凍結」を福利厚生として導入された「ジャパネットホールディングス」の田中様のお話を抜粋させていただきます。
福利厚生として卵子凍結制度の導入を選択された背景にはどのような課題があったのでしょうか。
田中様:家庭のある社員へのサポートは整っていたのですが、この部分を手厚くしていけばいくほど、子供を持ちたいと願っていても思うようにいかず悩んでいる社員や、いつか子どもを持ちたいけれど今は仕事に集中したいという社員を置いてきぼりにしてしまうという懸念がありました。卵子凍結制度は最もこの懸念を解消できる制度だと思い、導入に踏み切りました。「どんな人でも、どんな働き方でも歓迎している」という会社としての想いに寄り添える制度設計に近づけたと思います。
福利厚生導入の無料サポートも!
働く女性の心身の充実を支援する福利厚生パッケージ「Grace Care(グレイスケア)」をリリースしました。ベネフィットワン、ウェルボックス等福利厚生サービスとも連携しています。詳しくは、こちらからお問い合わせくださいませ。

名倉 優子 なぐら ゆうこ
日本産科婦人科学会専門医
グレイス杉山クリニックSHIBUYA (東京都渋谷区)
杉山産婦人科の医師・培養士による技術を用いた質の高い診療を提供。
将来の妊娠に備えたプレコンセプションケアと卵子凍結にフォーカスした診療。
スタッフは全員女性。明瞭な料金設定も人気!