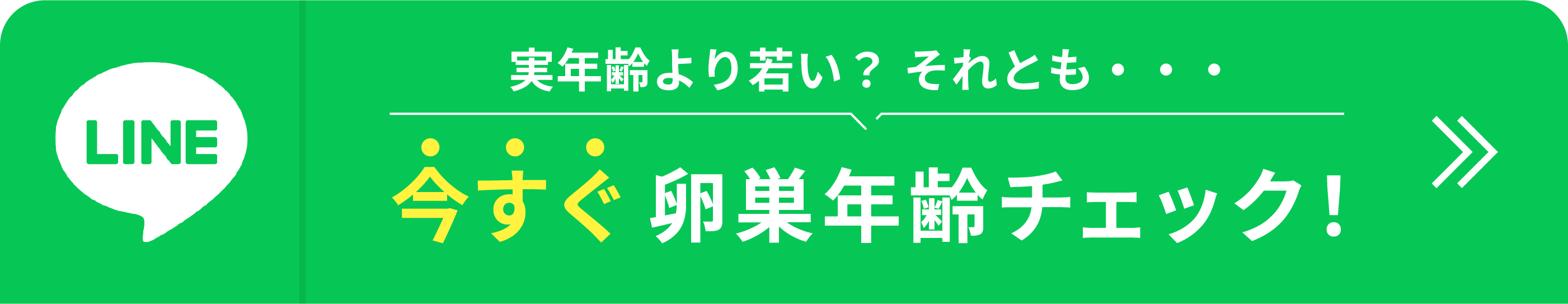6組に1組が不妊治療を受けると言われる日本。
妊活や不妊治療の現場の医師たちは、どんな想いを持って最前線に立っているのでしょうか。
普段は語られることがない、ドクターのパーソナルストーリー、第5話(前編、後編)は、「ファティリティクリニック東京」の小田原靖院長。
小田原院長は、海外で体外受精の最先端を学び、日本で初めて顕微授精を成功させた、まさに生殖医療業界の第一人者。
前編は、日本の生殖医療を切り開いてきた道のりについてたっぷりお話しを伺います。
小田原 靖
1982年 東京慈恵会医科大学 卒業。1987年に、豪州メルボルン王立婦人科病院生殖生物学教室に留学し、体外受精の最先端を学ぶ。また、スズキ病院産婦人科科長として、日本初の顕微授精児の誕生を主導。1996年、恵比寿にて「ファティリティ東京」を開業する。医師としてだけでなく、生殖医療のレベルの底上げにも寄与し、日本生殖医療標準化機関(JISART)理事も務める。日本生殖医学会認定 生殖医療専門医。
体外受精を切り開いた場所
──なぜ、医師の道に入ったのでしょうか。
実は、父は産婦人科の医師でした。
父が開業医だったことが、私の進路に影響を与えたのですが、もう一つ、大学の英語研究会サークルも大きなきっかけになりました。
サークルでは、様々な大学の学生が参加して英語を学んでいました。そこで、チーム対抗の英語ディベート大会があったのですが、その時のお題が「体外受精」だったのです。

1978年、世界で初めて体外受精が成功し、大きな話題になっていた頃でした。ディベート大会に備え、夏に男6人でむさ苦しく合宿やりましたね。体外受精について学んでみると、これがなかなか面白かった。私が医学部3年の時です。
産婦人科の先生に「生殖医療をやりたいのですが、医局に入れてもらえるでしょうか。」と掛け合ったのがきっかけで、今の縁につながっています
──生殖医療が進む、オーストラリアに留学されていますね。
世界で初めて体外受精で子どもが生まれたのは1978年。イギリスのロバート・エドワーズ教授率いるチームが、不妊に悩む夫婦に新たな道を切り開きました。
そして、2例目は、オーストラリア・メルボルンでした。両国は競っていたのですが、イギリスが1例目になったのです。その後、双方の考え方は大きく違いました。

イギリスは体外受精に成功した後、情報をシャットダウンし、留学生を受け入れなかったのです。一方、オーストラリアは、この技術は世界でどんどん広めるべきだという考えがあり、多くのセミナーを開いたり、海外から医師を呼び込みました。
私もオーストラリア行けば、最先端の生殖医療が学べるのではないかと思い、今までの業績、やりたい研究内容を手紙に書いて送りました。Eメールもなかった頃ですね。
そのかいあって、オーストラリアに渡ることになったのです。
チーム医療を学ぶ
── オーストラリアでの経験を教えてください。
師事したのは、「メルボルン王立婦人科病院(ロイヤル・ウィメンズ・ホスピタル)」のイアン・ジョンストン先生です。ジョンストン先生からは、本当にたくさんのことを教わりました。
私の人生のキーパーソンとも言える人物です。

ジョンストン先生がすごいのは、医療の面はもちろんですが、近代的な生殖医療システムを作ったという点です。日本では今、チーム医療はあたり前になっています。
生殖医療を行う現場には、看護師、培養師、カウンセラーが揃うチームがあるわけですね。
しかし、1980年代は医師が全てやっていた。そもそも胚培養士という人はいませんでした。
医師が培養液作って、採卵、卵子の培養をやっていたのです。これは決していいことではなくて、質の管理、取り違いのリスクを考えると怖いことなのです。

私が留学した80年代後半のオーストラリアでは、体外受精に取り組む「チーム」を作るということを一生懸命やっていました。
また、情報が少ない体外受精に対して、患者さんたちの会を作り、コミュニケーションが取れるようにネットワークを作ったりしていました。
まさに、今の生殖医療体制の礎を築いたのです。
看護師もドクターと同じ
──チームで臨む医療、どのような仕組みになっているのでしょうか。
30年ほど前の日本では、医師がトップ、培養師もあまりおらず、看護師も医師に比べて実質的な地位が低いという状況でした。
ところが、ジョンストン先生のチームでは、全てのスタッフが対等でした。当時の昼のミーティングでは、看護師もドクターに言いたいことをガンガン言っていた。
診療の責任や、最終的な決定は医師がします。それはどこの国も共通だと思うのですが、それに至る情報、卵子・受精卵の培養の状況、患者の精神状態の情報があって、正確な判断、診断ができる。

チームだからできることがあり、チーム医療が大事だということを叩き込まれました。私は、治療に関わる人が、対等な立場であるべきだと思っています。
「ジョンストン流」を取り入れ、開業してからずっと昼にミーティングをしています。チームメンバーが皆集まり、その日の患者さんの治療について確認し、認識を一致させる。
ジョンストン先生の教えに、少しでも報いれたらと思います。
日本初、顕微授精の成功
──海外から帰国し、日本で生殖医療の最先端を目指されたのですね。
オーストラリアでの2年の留学を終えたところ、ちょうどジョンストン先生から、良いお給料を保証するので研究を続けないかという有難いオファーがありました。
一方で、日本に帰らないと学位をもらえないという状況でもあり、後ろ髪を引かれながら帰国しました。

戻った日本の大学病院には、オーストラリアにあったような最先端の施設がありませんでした。
悶々としていたところ、東北大学名誉教授の鈴木 雅洲(すずき・まさくに)先生が、私の大学教授に、「小田原くんが暇そうだから、少し貸してくれないか?」と掛け合ってくれたんですね。
鈴木先生もオーストラリアで学んだ生殖医療の第一人者で、日本で「チーム医療」を根付かせようとしていました。そこに、私も参加したのです。
故・鈴木雅洲 医師:東北大学名誉教授。1983年日本で初めて体外受精児の誕生に成功する。日本の生殖医療の礎を築いた一人。1986年スズキ病院(現・スズキ記念病院)院長に就任した。
──スズキ病院産婦人科科長として、日本初の顕微授精の子どもの誕生を主導しました。
体外受精は卵管性不妊、卵管が詰まっている人に対しての治療ということで始まりました。卵子を体外に出して、精子を授精させるので、女性の卵管に問題がある人にはとても有効でした。

ただ、それが精子に対しては、思っていたほど有効ではありませんでした。では、精子に問題がある不妊の場合はどうしたらいいのか。
何とか有効な方法を探そうと様々なことが行われました。そこから「顕微授精」が生まれたのです。
高度な生殖医療が必要になるケースの3分の1は男性が原因で起きています。だから顕微授精という治療が有効になったのはとても画期的なことでした。
受け入れられなかった顕微授精
──当時の受け止め方はどうだったのでしょうか。
ただ、当時の反応はネガティブでした。「生殖医療がまた勇み足」、と言われました。
顕微授精で最初の子どもが生まれると、新聞記者が、病院の中に入って患者を探そうとする事案が起きました。1983年、東北大学で初めて、体外受精の子どもが誕生した時も大変でした。

医局のガードマンが、病院に入ろうとする記者を止めるということが起きたのです。今考えれば、将来、恩恵を受ける人が多い技術でしたが、当時は人体実験的なニュアンスで受け止められました。
例えば、受精卵などを培養する「培養士」は今では当たり前ですが、「医者でない人が培養した」ということで、非難されたりすることも起きました。
命につながる生殖医療において、常に倫理問題が議論され、「今の常識」が大きく非難された時代だったのです。
一方で、様々な批判に耐える科学的な根拠(エビデンス)を作らければいけないというのが、私たちのモチベーションになっていました。
患者にしっかり向き合いたい
──日本で作り96年開業、どんなチャレンジがあったでしょうか。
スズキ病院での仕事を終え、再び大学病院に戻りました。大学では限られた予算で、患者に満足してもらう医療を提供するのが難かしい状況でした。人も、場所もない、そして機械も古かった。
その中でも治療成績は要求されます。「こんな培養機では、なかなかいい受精卵に育たない」、そう思っても努力で乗り越えなければいけなかったのです。
そこで、大学病院という環境を越え、患者にしっかりと向き合える場所を作りたいと思い、1996年に開業しました。

最先端の機器をそろえてやっていこうと意気込んで始めました。とてもやりがいのあるものでしたね。
この時代には、大学病院で頑張って、より良い環境を目指して独立した先生たちがたくさんいたのです。
後半に続く──