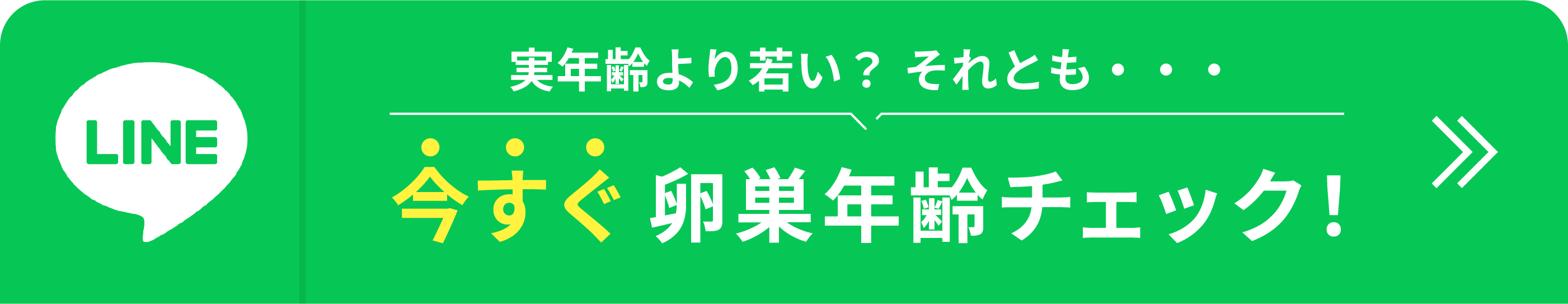卵子凍結の助成金について、多くの誤解を抱えていませんか?「国が全国一律で出している」「誰でも全額受けられる」「所得制限がある」といった情報は間違いかもしれません。この記事では、卵子凍結助成金の誤解と真実を徹底解説。国の制度と自治体の違い、年齢・健康状態の条件、助成上限額、所得制限の有無、助成の対象となるクリニックや説明会の要件など、あなたが知るべき正確な情報をお伝えします。
目次
はじめに 卵子凍結助成金の誤解を解き明かす
将来の妊娠に備え、卵子凍結を検討する方が増えています。その際、費用負担を軽減するために「助成金」の存在に注目する方も少なくありません。しかし、卵子凍結の助成金制度はまだ新しいこともあり、多くの誤解や不正確な情報が広まっているのが現状です。
「国が全国一律で助成してくれる」「誰でも受けられる」「費用は全額カバーされる」といった誤解は、正確な情報に基づかない計画を立ててしまう原因となりかねません。この記事では、卵子凍結助成金に関してよくある誤解をひとつひとつ丁寧に解き明かし、皆様が正しい知識を持って卵子凍結の検討を進められるよう、適用条件や注意点について詳しく解説します。
【誤解1】 卵子凍結の助成金は国が全国一律で出している?
【真実】 将来のための卵子凍結(社会的卵子凍結)は自治体で助成をしている
「卵子凍結の助成金は国が全国一律で提供している」という認識は、誤りです。
かつて存在した国の「特定不妊治療費助成制度」は、体外受精や顕微授精などの不妊治療に対するものであり、将来のための卵子凍結(特に社会的卵子凍結)を直接的に対象とするものではありませんでした。現在、この国の制度は廃止され、不妊治療への助成は地方自治体(都道府県や市区町村)の取り組みが中心となっています。
卵子凍結に関する助成金も、その多くは各地方自治体が独自に実施している制度です。そのため、助成の有無、対象となる条件、助成額などは、お住まいの自治体によって大きく異なります。
一部の自治体では、がん治療など医学的な理由で生殖機能が低下する可能性のある方(医学的適応卵子凍結)を対象とした助成を行っているほか、近年では将来の妊娠に備える「社会的卵子凍結」に対しても助成を開始する自治体が増えています。しかし、これらの制度は全国一律ではなく、自治体ごとの判断と財政状況に基づいて設計されています。
以下の表で、国と自治体の助成制度の違いを整理します。
| 項目 | 国の制度(特定不妊治療費助成制度) | 自治体の制度(卵子凍結助成金) |
| 主な対象 | 体外受精・顕微授精などの不妊治療 | 卵子凍結(医学的適応・社会的卵子凍結) |
| 実施主体 | 国(現在は廃止され自治体へ移行) | 各地方自治体(都道府県・市区町村) |
| 制度の統一性 | かつては全国共通の基準があった | 自治体ごとに内容が大きく異なる |
| 所得制限 | かつては所得制限があった | 所得制限がない自治体が多い |
ご自身の居住地の自治体がどのような助成制度を設けているか、必ず公式ウェブサイトなどで最新情報を確認することが重要です。
【誤解2】 卵子凍結の助成金は誰でも受けられる?
【真実】 助成金には年齢や健康状態の条件がある
「卵子凍結の助成金は、希望すれば誰でも受けられる」というのも、よくある誤解の一つです。
実際には、多くの自治体で助成金を受けるための明確な条件が設定されています。主な条件として挙げられるのは、以下の点です。
- 年齢制限: ほとんどの自治体で、卵子凍結を実施する際の年齢や、助成金を申請する際の年齢に上限が設けられています。例えば、「採卵を実施した日における年齢は18歳から39歳まで」といった具体的な年齢制限が一般的です。これは、年齢が上がるにつれて卵子の質や採卵数に影響が出る可能性が高まるため、助成の費用対効果を考慮しているためと考えられます。
- 居住地の要件: 助成金を申請する自治体に、住民票があることが必須条件となります。転居を検討している場合は、事前に確認が必要です。
- 健康状態(医学的適応の有無): 助成制度によっては、医学的な理由(がん治療や自己免疫疾患など、将来的に妊娠が困難になる可能性のある疾患)による卵子凍結のみを対象としている場合があります。これは「医学的適応卵子凍結」と呼ばれます。一方で、健康な女性が将来の出産に備えるための「社会的卵子凍結」も助成対象とする自治体も増えていますが、その場合でも年齢制限などの条件は厳しく設定される傾向があります。
- 医師の判断: 卵子凍結が医学的に適切であると、医師が判断していることも条件となる場合があります。
これらの条件は自治体によって大きく異なるため、ご自身が助成の対象となるかどうかを、必ず各自治体の最新情報で確認することが不可欠です。安易に「誰でも受けられる」と思い込まず、事前にしっかりと情報収集を行いましょう。

【誤解3】 卵子凍結の費用は全額助成される?
【真実】 助成される金額には上限がある(助成対象となる費用の範囲)
「卵子凍結にかかる費用は、助成金で全額カバーされる」というのも、残念ながら誤解です。
卵子凍結の助成金制度は、自己負担を軽減するためのものであり、費用の全額が助成されるケースは極めて稀です。ほとんどの自治体では、助成される金額に上限額が設定されており、費用の「一部」が助成される形になります。
例えば、「卵子凍結を実施した年度に上限20万円」や「次年度以降の保管費用を一律2万円(年数制限あり)」といった形で上限が定められていることが多く、実際の費用が上限額を超えた場合は、その超過分は自己負担となります。
また、助成対象となる費用の範囲も限定されていることが多いため、注意が必要です。一般的に助成対象となるのは、以下のような費用です。
- 採卵手術費
- 卵子凍結費用
- 薬剤費(排卵誘発剤など)
- 検査費(ホルモン検査、感染症検査など)
- 凍結卵子保管料(年単位で発生する維持費用)
特に卵子保管料は、卵子凍結後の毎年発生するランニングコストであり、多くの自治体で助成対象とされています。卵子凍結を検討する際には、この保管料も含めた長期的な費用負担を考慮に入れる必要があります。
一方で、助成対象とならないことが多い費用も存在します。これには以下のようなものが挙げられます。
- 初診料、再診料、診察料
- カウンセリング費用
- 交通費、宿泊費
助成金額の上限や対象となる費用の詳細については、必ず申請を検討している自治体の最新の募集要項やウェブサイトで確認し、トータルでかかる費用と自己負担額を把握することが重要です。
【誤解4】 所得の制限がある?
【真実】 卵子凍結の助成金には所得制限はない
「卵子凍結の助成金には所得制限があるのではないか」と心配される方もいますが、多くの自治体で実施されている卵子凍結助成金制度には、所得制限は設けられていません。
かつて国の制度であった「特定不妊治療費助成制度」には、夫婦合算の所得制限が設けられていました。このため、不妊治療の助成金には所得制限があるというイメージが残っているのかもしれません。しかし、卵子凍結に対する自治体独自の助成制度においては、所得の多寡にかかわらず、対象条件を満たすすべての希望者が申請できるケースがほとんどです。
これは、卵子凍結が女性のライフプランの選択肢を広げ、将来の出産を支援するという目的のもと、より多くの人が利用できるように設計されているためと考えられます。
ただし、今後、一部の自治体で独自の基準を設ける可能性もゼロではありませんので、最終的には、申請を検討している自治体の公式情報を確認することが最も確実です。

【誤解5】 助成金を受ける場合、その自治体にあるクリニックで卵子凍結をしないといけない?
【真実】 自治体に限らない場合もある
「卵子凍結の助成金を受けるためには、助成金を申請する自治体内にあるクリニックで卵子凍結を行わなければならない」というのも、必ずしも真実ではありません。
多くの自治体では、助成金を申請する方の住民票がその自治体にあれば、全国の提携医療機関や特定の基準を満たす医療機関であれば、その自治体外のクリニックで卵子凍結を行った場合でも助成の対象となるケースが多いです。
一例として、東京都千代田区や港区における東京都の卵子凍結助成金への上乗せは、千代田区・港区外のクリニックでも適用になります。
重要なのは、助成金を申請する自治体が指定する「医療機関の要件」を満たしているかどうかです。「日本産科婦人科学会に生殖補助医療実施登録施設として登録されている医療機関」という要件が一般的です。
しかし、ごく一部の自治体では、地域医療の振興や連携強化などの目的で、自治体内の医療機関に限定していたり、助成額に金額差がある場合も存在します。そのため、卵子凍結を行うクリニックを選ぶ前に、必ず助成金申請を予定している自治体のウェブサイトや担当窓口で、対象となる医療機関の範囲について確認することが不可欠です。
遠方のクリニックでの治療を検討している場合は、特にこの点に注意し、事前に確認を怠らないようにしましょう。
【誤解6】 自治体の説明会を受けないと卵子凍結はスタートできない?
【真実】 説明会前でも卵子凍結をスタートしてもOK
「自治体が開催する説明会に参加しないと、卵子凍結をスタートできない」という認識も、誤解であることが多いです。
卵子凍結は、女性の年齢によって卵子の質や数が変動するため、時間との勝負となる側面もあります。そのため、説明会の開催を待たずに、まずはクリニックでのカウンセリングや検査を進め、卵子凍結の準備を始めることは十分に可能です。
ただし、一部の自治体では、説明会への参加が助成金申請の要件となっている場合や、説明会で配布される特定の資料やコードが必要となる場合も存在します。また、説明会で申請に必要な書類が配布されたり、手続きに関する重要な注意事項が説明されたりすることもあります。
したがって、説明会への参加が必須かどうか、また参加することでどのようなメリットがあるかについては、必ず申請を検討している自治体の公式情報を確認するようにしてください。基本的には、説明会を待たずに卵子凍結のプロセスを開始しても問題ないケースが多いですが、念のため確認することで、後のトラブルを防ぐことができます。
まとめ
卵子凍結の助成金は、国の特定不妊治療費助成制度とは異なり、各自治体が独自に実施しているため、その内容は地域によって大きく異なります。助成の対象となるには年齢や健康状態などの条件があり、助成される金額にも上限が設けられています。しかし、所得による制限は基本的にありません。また、必ずしも居住地のクリニックに限定されるわけではなく、自治体の説明会受講前でも卵子凍結を開始できるケースもあります。正確な情報を得るためには、居住地の自治体窓口や公式ウェブサイトで最新の情報を確認することが最も重要です。
卵子凍結について興味がある方・実際に検討されている方は、ぜひGrace Bank(グレイスバンク)の無料セミナー等もご活用ください。より詳しく卵子凍結の相談・検討をしたい場合は無料の個別相談がおすすめです。
Grace Bank(グレイスバンク)所属スタッフが、グレイスバンクのサービス内容・ご利用の流れ・お手続き・クリニック選び等のご不明な点について個別にお応えします。ぜひご活用ください。

名倉 優子 なぐら ゆうこ
日本産科婦人科学会専門医
グレイス杉山クリニックSHIBUYA (東京都渋谷区)
杉山産婦人科の医師・培養士による技術を用いた質の高い診療を提供。
将来の妊娠に備えたプレコンセプションケアと卵子凍結にフォーカスした診療。
スタッフは全員女性。明瞭な料金設定も人気!