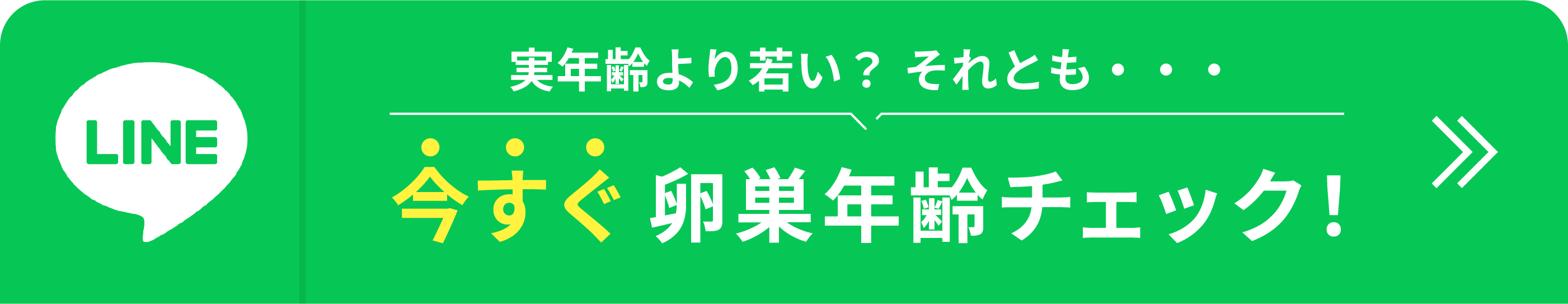流産は深い悲しみをもたらし、特に繰り返す流産に悩む方にとって、その原因と対策は切実な願いです。流産の原因は多岐にわたりますが、特に「卵子の質」が深く関わることが分かっています。本記事では、加齢による卵子の老化や染色体異常など、卵子の質が流産を引き起こすメカニズムを解説。卵子の質を改善し流産リスクを減らすための生活習慣、サプリメント、専門的治療法まで、具体的なアプローチを網羅的に解説します。繰り返す悲しみを乗り越え、未来への希望を見出すための確かな知識とヒントがここにあります。
目次
流産の主な原因と卵子の役割
流産の原因は多岐にわたる
流産は、妊娠22週未満で妊娠が中断してしまうことを指し、その原因は一つではなく、多岐にわたります。妊娠初期の流産の多くは、胎児側の要因、特に染色体異常によるものですが、母体側の要因も無視できません。原因を理解することは、繰り返す流産を予防し、適切な対策を講じる上で非常に重要です。
流産の主な原因は以下の通りです。
| 原因の分類 | 具体的な内容 | 卵子との関連性 |
| 胎児側の要因 | 染色体異常(受精卵の染色体の数や構造の異常) | 流産の約60-70%を占める主要な原因であり、その大部分は卵子の質の低下に起因します。 |
| 母体側の要因 | 子宮の異常(子宮筋腫、子宮奇形、子宮内膜ポリープ、子宮腔癒着など) | 受精卵の着床環境に直接影響を与えますが、卵子の質とは直接的な関連性はありません。 |
| 母体側の要因 | 内分泌異常(黄体機能不全、甲状腺機能異常、糖尿病、高プロラクチン血症など) | ホルモンバランスの乱れが卵子の成熟や受精卵の着床・維持に影響を与える可能性があります。 |
| 母体側の要因 | 血液凝固異常(抗リン脂質抗体症候群など) | 胎盤形成に必要な血流に影響を及ぼし、受精卵の発育を阻害することがありますが、卵子の質とは直接関連しません。 |
| 母体側の要因 | 免疫学的因子(NK細胞活性の異常など) | 母体の免疫系が受精卵を異物と認識し攻撃することで流産に至る可能性があり、卵子の質とは直接関連しません。 |
| 母体側の要因 | 感染症(子宮内感染など) | 子宮内の環境を悪化させ、流産を引き起こすことがありますが、卵子の質とは直接関連しません。 |
| 母体側の要因 | 生活習慣(過度の喫煙、飲酒、肥満、ストレスなど) | 母体の健康状態全体に影響を与え、間接的に卵子の質や子宮環境に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
流産における卵子の質の重要性
流産の原因の中で最も頻度が高いのは、受精卵の染色体異常です。そして、この受精卵の染色体異常の大部分は、卵子の質の低下に起因していることが明らかになっています。卵子は、女性が生まれた時からその数を持ち、排卵されるまで体内で成熟を待つため、加齢とともにその質が低下する傾向にあります。
卵子の質とは、単に見た目の良し悪しだけでなく、正常な減数分裂を行う能力、適切なエネルギーを供給するミトコンドリアの機能、そして酸化ストレスから自身を守る能力など、多岐にわたる要素によって評価されます。これらの機能が低下した卵子は、受精後に正常な細胞分裂ができず、染色体の数や構造に異常が生じやすくなります。
具体的には、質の低い卵子では、染色体が均等に分配されない「減数分裂異常(染色体不分離)」が起こりやすくなります。これにより、染色体数が過剰になったり不足したりする「異数性」を持つ受精卵が形成されます。このような染色体異常を持つ受精卵は、たとえ着床したとしても、その後の成長が停止したり、早期に流産に至る可能性が非常に高くなります。
したがって、流産を繰り返す場合や、高齢での妊娠を希望する場合には、卵子の質が流産に与える影響を深く理解し、その改善に向けたアプローチを検討することが極めて重要になります。
加齢と卵子の質の低下が流産に与える影響
妊娠を望む多くの方にとって、年齢は重要な要素となります。特に、女性の年齢と卵子の質は密接に関係しており、流産のリスクに大きな影響を与えることが知られています。この章では、加齢が卵子の質にどのように作用し、それが流産とどのように結びつくのかを詳しく解説します。
卵子の老化とは何か
女性が体内で持つ卵子の数は、生まれた時から決まっており、新しく作られることはありません。思春期以降、毎月排卵が起こり、卵子の数は減少し続けていきます。この卵子たちは、女性の体と同じ年月を過ごすため、加齢とともに様々な変化が生じます。これが「卵子の老化」と呼ばれる現象です。
卵子の老化は、主に以下の質的な変化を伴います。
- 染色体異常の増加: 卵子が成熟する過程で行われる減数分裂において、年齢とともにエラーが起こりやすくなります。これにより、染色体の数や構造に異常を持つ卵子が増加します。受精卵の染色体異常は、流産の最も一般的な原因の一つです。
- ミトコンドリア機能の低下: 卵子の中にあるミトコンドリアは、細胞のエネルギー源となるATPを生成する重要な役割を担っています。加齢によりミトコンドリアの機能が低下すると、卵子のエネルギー産生能力が衰え、受精や初期胚の発生に必要なエネルギーが不足し、流産につながる可能性があります。
- 細胞小器官の劣化: 卵子内のその他の細胞小器官(例えば、小胞体やゴルジ体など)も、加齢とともに機能が低下することがあります。これらの機能低下は、卵子の正常な発達や受精後の胚発生に悪影響を及ぼす可能性があります。
これらの卵子の質的変化は、妊娠の成立を困難にするだけでなく、妊娠が成立しても流産のリスクを高める主要な要因となります。
年齢が流産率に及ぼす具体的な影響
女性の年齢が上がるにつれて、流産率は統計的に顕著に上昇することが示されています。これは、前述した卵子の老化、特に染色体異常を持つ卵子の増加が主な原因です。
流産率/総妊娠率
- 30歳:15.8%
- 31歳:16.1%
- 32歳:17.9%
- 33歳:18.4%
- 34歳:19.8%
- 35歳:19.8%
- 36歳:21.7%
- 37歳:23.3%
- 38歳:26.2%
- 39歳:28.9%
※出典:日本産科婦人科学会 2021年ARTデータブックより
https://www.jsog.or.jp/activity/art/2021_JSOG-ART.pdf
この表からもわかるように、30代後半から流産率の上昇傾向が顕著になり、40代に入るとそのリスクは急激に高まります。特に40歳を超えると、自然流産の半分以上が胎児の染色体異常に起因すると言われています。
現代社会では、女性の社会進出やライフスタイルの変化に伴い、初産年齢が上昇する傾向にあります。これにより、妊娠を希望する年齢が高齢化し、結果として流産に直面するケースも増加しています。年齢は変えることのできない要因ですが、自身の年齢と卵子の質、そして流産リスクの関係性を理解することは、適切な情報に基づいた選択をする上で非常に重要です。
卵子の質が流産を引き起こすメカニズム
流産は様々な要因によって引き起こされますが、その中でも卵子の質は、受精から初期胚発生、そして着床後の胎児の成長に決定的な影響を与え、流産リスクと密接に関わっています。ここでは、卵子の質が流産を引き起こす主要なメカニズムについて、科学的根拠に基づいて詳しく解説します。
染色体異数性と流産
流産の最も一般的な原因は、胎児の染色体異常であるとされています。特に妊娠初期の流産の約60~70%は、染色体異常が原因と考えられており、その大部分は卵子の染色体異常に由来します。
卵子が成熟する過程で行われる「減数分裂」は、染色体の数を半分にし、受精に備える重要なプロセスです。しかし、この減数分裂の際にエラーが生じると、染色体の数や構造に異常がある卵子(染色体異数性卵子)ができてしまいます。このような卵子が受精すると、染色体異常を持つ受精卵となり、正常な発生が妨げられ、流産に至る可能性が高くなります。
具体的な染色体異数性の例としては、特定の染色体が3本存在する「トリソミー」(例:21トリソミー)や、特定の染色体が1本しかない「モノソミー」などがあります。これらの異常を持つ胚は、多くの場合、子宮内で正常に成長できず、流産となります。
| 染色体異常の種類 | 内容 | 流産との関連 |
| トリソミー | 特定の染色体が通常より1本多い(計3本)状態 | 最も一般的な流産の原因。特に16番、22番、21番染色体のトリソミーが多く見られます。 |
| モノソミー | 特定の染色体が通常より1本少ない(計1本)状態 | 非常に早期の流産を引き起こすことが多く、特にX染色体以外の常染色体モノソミーは致死的です。 |
| 多倍体 | 染色体セット全体が複数ある状態(例:3倍体、4倍体) | 受精卵が複数の精子と受精するなどして発生し、通常は早期の流産につながります。 |
| 構造異常 | 染色体の一部が欠損、重複、転座している状態 | 流産や胎児の先天性異常の原因となる場合があります。 |
卵子の質が低下すると、この減数分裂エラーのリスクが高まり、結果としてトリソミーやモノソミーなどの染色体異数性を持つ受精卵が形成されやすくなるため、流産率が上昇すると考えられています。
卵子のミトコンドリア機能とエネルギー不足
ミトコンドリアは、細胞内でエネルギー(ATP)を生産する「細胞の発電所」として知られています。卵子は、その成熟、受精、そして受精後の初期胚の細胞分裂といった極めてエネルギーを必要とするプロセスを担うため、他の細胞に比べて大量のミトコンドリアを含んでいます。
卵子のミトコンドリアが正常に機能し、十分なエネルギーを供給できなければ、以下のような問題が生じ、流産のリスクが高まります。
- 卵子の成熟不全: 十分なエネルギーがないと、卵子が最終的な成熟段階に到達できず、受精能力が低下します。
- 受精障害: 精子との融合や前核形成など、受精の各ステップに必要なエネルギーが不足し、受精がうまくいかないことがあります。
- 初期胚発生の停止: 受精後の細胞分裂(卵割)には膨大なエネルギーが必要です。ミトコンドリア機能が低下していると、胚の分裂が途中で停止したり、形態異常が生じたりし、結果として流産に至ります。特に、DNAの複製や修復、染色体を正確に分配するための紡錘体形成には、ATPが不可欠です。
加齢に伴い、卵子内のミトコンドリアの数や機能が低下することが知られており、これが卵子の質の低下、ひいては流産リスクの上昇に繋がる重要なメカニズムの一つです。
酸化ストレスと卵子のダメージ
酸化ストレスとは、体内で発生する「活性酸素種(ROS)」と、それを無毒化する「抗酸化物質」のバランスが崩れ、活性酸素種が過剰になった状態を指します。活性酸素種は、細胞にダメージを与える性質があります。
卵子は、その代謝活性の高さや、細胞膜に多くの不飽和脂肪酸を含む特性から、酸化ストレスの影響を受けやすい細胞であると考えられています。過剰な活性酸素種は、卵子に以下のような様々なダメージを与え、流産のリスクを高めます。
- DNA損傷: 卵子の核内にあるDNAに直接的な損傷を与え、染色体異常のリスクを高めます。
- ミトコンドリア損傷: ミトコンドリア自体も活性酸素種の標的となりやすく、ダメージを受けることでエネルギー産生能力がさらに低下します。これにより、卵子の成熟や胚発生に必要なエネルギーが不足し、機能不全を招きます。
- 細胞膜・タンパク質の損傷: 卵子の細胞膜や重要なタンパク質が酸化されることで、受精能力が低下したり、胚の正常な発生に必要な情報伝達が阻害されたりします。
喫煙、過度の飲酒、不健康な食生活、ストレス、環境汚染物質への曝露などは、体内の酸化ストレスを増大させる要因となります。これらの要因が卵子の質に悪影響を及ぼし、結果的に流産のリスクを高める可能性があります。
繰り返す流産(不育症)と卵子の関係

不育症の定義と検査
妊娠を希望する夫婦にとって、流産は計り知れない悲しみをもたらします。特に、流産を繰り返す場合、それは「不育症」と診断される可能性があります。不育症とは、一般的に2回以上、または3回以上の連続した流産、死産、あるいは早期新生児死亡を経験した場合に診断される状態を指します。流産は妊娠全体の約15%で起こると言われていますが、そのうちの約1%が不育症であるとされています。
不育症の原因は多岐にわたり、特定の要因が特定できる場合と、原因が特定できない「原因不明不育症」の場合があります。不育症の診断のためには、以下のような様々な検査が行われます。
| 検査項目 | 検査内容と目的 |
| 夫婦染色体検査 | 夫婦それぞれの染色体に異常がないかを確認します。染色体転座などが流産の原因となることがあります。 |
| 子宮形態検査 | 子宮の形に異常(子宮奇形、子宮筋腫、子宮内膜ポリープなど)がないかを超音波検査や子宮卵管造影検査、子宮鏡検査などで調べます。 |
| 内分泌検査 | 甲状腺機能異常(橋本病、バセドウ病など)や糖尿病、高プロラクチン血症など、内科疾患が流産に関与していないかを確認します。 |
| 血液凝固系検査 | 血液が固まりやすくなる病気(抗リン脂質抗体症候群など)がないかを調べます。血液が固まりやすいと、胎盤への血流が悪くなり流産のリスクが高まります。 |
| 免疫系検査 | 母体の免疫が胎児を異物と認識し攻撃してしまう可能性がないかを調べることがあります。 |
これらの検査によって原因が特定されれば、それに応じた治療法を選択することができます。しかし、不育症の約半数は、これらの検査ではっきりとした原因が見つからない「原因不明不育症」と診断されます。この原因不明不育症の中に、卵子の質の問題が大きく関わっているケースが少なくありません。
不育症における卵子要因の重要性
不育症の原因が特定できない場合でも、卵子の質が不育症の背景にある重要な要因である可能性が近年注目されています。特に、原因不明不育症と診断されたケースにおいて、卵子の質の低下が根本的な原因となっていることが増えています。
卵子の質が低下している場合、受精卵の染色体異常のリスクが高まります。受精卵の染色体異常は、流産の最も一般的な原因であり、妊娠初期の流産の約60~80%を占めると言われています。質の低い卵子から作られた受精卵は、たとえ着床したとしても、その後の発生・成長がうまくいかず、結果として流産に至りやすくなるのです。
加齢は卵子の質を低下させる主要な要因ですが、年齢だけが卵子の質に影響を与えるわけではありません。酸化ストレス、ミトコンドリア機能の低下、生活習慣(食生活、運動不足、睡眠不足、ストレスなど)、環境因子なども卵子の質に悪影響を及ぼし、不育症のリスクを高める可能性があります。これらの要因によって卵子の質が低下すると、受精卵が正常に細胞分裂を進められなかったり、着床後の成長に必要なエネルギーを十分に供給できなかったりするため、繰り返す流産に繋がると考えられています。
したがって、不育症の診断において、従来の検査で原因が特定できない場合でも、卵子の質に着目し、その改善を目指すアプローチが、繰り返す悲しみを乗り越えるための重要な鍵となります。
卵子の質を改善し流産リスクを減らすアプローチ
流産の悲しみを繰り返さないために、卵子の質を改善することは非常に重要なアプローチです。日々の生活習慣の見直しから、専門的な医療介入まで、多角的な視点から卵子の健康を高める方法を探りましょう。
生活習慣の見直しで卵子の質を高める
卵子の質は、遺伝的な要因だけでなく、私たちの日常生活における習慣にも大きく影響されます。健康的な生活習慣を心がけることで、卵子の質を向上させ、流産のリスクを減らすことが期待できます。
食生活の改善と栄養バランス
卵子の健康を保つためには、バランスの取れた食生活が不可欠です。特に、細胞の老化を防ぐ抗酸化作用の高い食品を積極的に摂取することが推奨されます。新鮮な野菜や果物、ナッツ類、全粒穀物、良質なタンパク質(魚、鶏むね肉、豆類)を意識して取り入れましょう。一方で、加工食品、過剰な糖分や脂質、カフェインの過剰摂取は避けるべきです。また、葉酸、ビタミンD、鉄分、亜鉛など、生殖機能に関わる特定の栄養素が不足しないよう、食事内容を見直すことが重要です。
適度な運動と質の良い睡眠
適度な運動は、血行を促進し、卵巣への血流を改善することで卵子の質に良い影響を与えます。ウォーキング、ヨガ、軽いジョギングなど、無理なく続けられる有酸素運動がおすすめです。ただし、過度な運動はかえって体に負担をかける可能性があるため注意が必要です。また、質の良い睡眠は、ホルモンバランスの調整や細胞の修復に不可欠です。十分な睡眠時間を確保し、規則正しい睡眠サイクルを確立することで、体全体の健康、ひいては卵子の質の向上に繋がります。
ストレスマネジメントの重要性
慢性的なストレスは、ホルモンバランスに悪影響を与え、卵子の成熟や排卵に支障をきたす可能性があります。ストレスを効果的に管理することは、卵子の質を保つ上で非常に重要です。リラックスできる趣味を見つける、瞑想や深呼吸を取り入れる、アロマセラピーを利用するなど、自分に合ったストレス解消法を見つけましょう。必要であれば、専門家への相談も検討し、心の健康を保つことも大切です。
卵子の質改善に役立つサプリメント
食事だけでは補いきれない栄養素を補うために、特定のサプリメントが卵子の質改善に役立つとされています。しかし、サプリメントはあくまで補助的なものであり、必ず医師や薬剤師と相談の上で摂取するようにしましょう。
還元型コエンザイムの効果
還元型コエンザイムは、細胞内のミトコンドリアに多く存在し、エネルギー産生に不可欠な役割を担っています。卵子の老化に伴いミトコンドリアの機能が低下することが指摘されており、コエンザイムQ10の摂取は、卵子のミトコンドリアの活性化を促し、エネルギー不足を改善することで、卵子の質の向上に寄与する可能性が示唆されています。また、強力な抗酸化作用も持ち、卵子を酸化ストレスから守る働きも期待できます。
| 期待される効果 | 摂取のポイント |
| 卵子のエネルギー産生向上 | 一般的に1日100~600mgが推奨されますが、医師と相談して適切な量を決定してください。 |
| 強力な抗酸化作用 | 脂溶性のため、食事と一緒に摂取すると吸収率が高まります。 |
| ミトコンドリア機能の改善 | 効果を実感するには数ヶ月間の継続摂取が必要な場合があります。 |
DHEAなどその他のサプリメント
DHEA(デヒドロエピアンドロステロン)は、副腎で産生されるホルモンの一種で、卵巣機能の改善やAMH値(抗ミュラー管ホルモン)の上昇に繋がる可能性が報告されています。しかし、DHEAはホルモンであるため、必ず医師の指導のもとで使用し、自己判断での摂取は避けてください。その他にも、卵子の質改善に期待されるサプリメントとして、葉酸、ビタミンD、L-カルニチン、イノシトール、α-リポ酸などが挙げられます。これらのサプリメントも、個々の状態に合わせて医師と相談し、適切なものを選択することが重要です。
| サプリメント | 期待される効果 | 備考 |
| DHEA | 卵巣機能の改善、AMH値の上昇 | ホルモン製剤であり、必ず医師の指導のもとで摂取。副作用のリスクも考慮。 |
| 葉酸 | 神経管閉鎖障害のリスク低減、卵子や精子のDNA合成に関与 | 妊娠を計画する女性には必須。 |
| ビタミンD | ホルモンバランスの調整、着床環境の改善 | 不足している場合に補給。 |
| L-カルニチン | ミトコンドリアの脂肪酸輸送を助け、エネルギー産生をサポート | コエンザイムQ10と併用されることも。 |
| イノシトール | 卵子の成熟促進、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の改善 | |
| α-リポ酸 | 強力な抗酸化作用、ミトコンドリア機能のサポート | 水溶性・脂溶性の両方で作用。 |
専門的な検査と治療法
生活習慣の改善やサプリメントの摂取に加えて、医療機関で受けられる専門的な検査や治療法も、流産リスクを減らすための重要な選択肢となります。
着床前診断(PGT-A)の役割
着床前診断(PGT-A:Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy)は、体外受精によって得られた受精卵(胚)を子宮に戻す前に、その染色体数を調べる検査です。流産の主な原因の一つである受精卵の染色体異数性を事前に確認することで、染色体異常のない胚を選んで移植し、流産のリスクを低減することを目的としています。特に、繰り返す流産を経験している方や、高齢で染色体異常のリスクが高い方にとって、有効な選択肢となり得ます。日本では、日本産科婦人科学会の承認のもと、特定の施設で実施されています。メリットとしては、流産率の低下や妊娠までの期間短縮が期待できる一方で、胚への影響や倫理的な問題、費用などのデメリットも考慮する必要があります。
体外受精における卵子の質評価
体外受精の過程では、採卵された卵子の成熟度や形態が評価されます。卵子の成熟度(MII期卵子であるかなど)は、受精の成否に直結します。また、透明帯の厚さや卵細胞質の均一性、極体の形態なども、卵子の質を間接的に示す指標となります。さらに、受精後の受精率や胚盤胞到達率、胚のグレードなども、卵子の質を総合的に評価する上で重要な情報となります。これらの評価を通じて、より質の高い卵子や胚を選び、着床・妊娠の可能性を高めることが目指されます。ただし、形態的な評価だけで卵子の質を完全に判断することは難しく、見た目が良くても染色体異常を持つ場合があることも理解しておく必要があります。
繰り返す流産を乗り越えるための心のケア

精神的サポートの重要性
流産を経験することは、身体的な負担だけでなく、計り知れない精神的な苦痛を伴います。特に繰り返す流産は、「なぜ自分だけが」「また同じことが起こるのではないか」という強い不安や絶望感、そして自責の念を引き起こすことがあります。このような深い悲しみや喪失感は、時にうつ病や適応障害といった心の病へとつながる可能性も否定できません。
この困難な時期を乗り越えるためには、周囲からの理解と精神的なサポートが不可欠です。パートナーとの関係性、家族や友人とのコミュニケーション、そして同じ経験を持つ人々とのつながりが、心の回復において大きな支えとなります。
| サポートの種類 | 具体的な内容 |
| パートナーとの支え合い | お互いの感情を共有し、悲しみを分かち合うことで、孤立感を軽減し、夫婦の絆を深めることができます。 |
| 家族・友人からの理解 | 無理に励ますのではなく、ただ話を聞いてくれる、そばにいてくれるといった姿勢が心の安定につながります。 |
| 自助グループへの参加 | 同じ経験を持つ人々と交流することで、共感を得られ、自身の感情が正常であることを認識し、孤独感を解消できます。 |
特にパートナーとの間では、お互いの悲しみの表現方法が異なる場合があるため、率直なコミュニケーションを心がけることが重要です。感情を共有し、支え合うことで、この困難な時期を共に乗り越える力が生まれます。
専門家への相談とカウンセリング
流産による精神的な負担が大きく、日常生活に支障をきたすような場合は、専門家への相談やカウンセリングを検討することが非常に重要です。専門家は、客観的な視点から心の状態を評価し、適切なサポートや治療を提供してくれます。
不妊治療や不育症の専門クリニックには、不妊カウンセラーや臨床心理士が常駐している場合が多く、流産後の悲嘆のケアや、次の妊娠への不安に対する心理的サポートを提供しています。また、必要に応じて心療内科医や精神科医との連携も可能です。
| 専門家の種類 | 提供されるサポート・治療 |
| 不妊・不育症カウンセラー | 流産による悲嘆のケア、精神的ストレスの軽減、夫婦関係の調整、次のステップへの心の準備など、心理的サポートを提供します。 |
| 臨床心理士・公認心理師 | 専門的なカウンセリングや心理療法を通じて、感情の整理、ストレス対処法の習得、トラウマケアなどを行います。 |
| 心療内科医・精神科医 | うつ病や適応障害などの精神疾患が疑われる場合、診断と薬物療法を含む専門的な治療を提供します。 |
専門家によるカウンセリングは、自身の感情を安全な場所で吐き出し、整理する機会となります。また、悲しみや不安と向き合い、それらを乗り越えるための具体的な方法を学ぶことができます。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることで、心の回復への道が開かれるでしょう。
まとめ
流産は多岐にわたる原因で起こりますが、特に卵子の質が深く関わっています。加齢による卵子の老化は、染色体異常などのリスクを高め、流産率の上昇につながる主要な理由の一つです。繰り返す流産(不育症)においても、卵子要因の重要性は増しています。しかし、生活習慣の見直し、適切な栄養摂取、サプリメントの活用、そして着床前診断(PGT-A)などの専門的な治療を通じて、卵子の質を改善し、流産リスクを低減できる可能性があります。悲しみを乗り越え、前向きに進むためには、正しい知識と心のケアが不可欠です。

名倉 優子 なぐら ゆうこ
日本産科婦人科学会専門医
グレイス杉山クリニックSHIBUYA (東京都渋谷区)
杉山産婦人科の医師・培養士による技術を用いた質の高い診療を提供。
将来の妊娠に備えたプレコンセプションケアと卵子凍結にフォーカスした診療。
スタッフは全員女性。明瞭な料金設定も人気!